第5回 ジョージ・エラリー・ヘールの「大きいことはいいことだ!」
『パロマーの巨人望遠鏡(上)(下)』 (ウッドベリー著,岩波文庫)

 SF作家の笹本祐一氏の名言(?)に、「日本人は甘い、酸っぱい、塩からい、苦い、うまいの五つの味覚を持っているが、アメリカ人には三つしかない。甘い、脂っこい、でかいだ」というのがある。
SF作家の笹本祐一氏の名言(?)に、「日本人は甘い、酸っぱい、塩からい、苦い、うまいの五つの味覚を持っているが、アメリカ人には三つしかない。甘い、脂っこい、でかいだ」というのがある。
いやもうその通り、アメリカに美味しいものがないわけではないのだけれど、そこらでちょっと飯をと思うと、買った缶飲料は涙が出るほど甘い緑茶だったり、朝食はバターたっぷりのスクランブルエッグと脂ぎとぎとのベーコンだったり、ファストフードのピザもハンバーガーも半端なく大きかったり……。
なかでも「でかい」というのは「強い」と結びついて、アメリカという国の「かくあらねばならない」という強迫観念の中心に位置している。高校における男子の花形は、筋肉隆々のフットボールの選手で、女子はと言えばグラマーなチアガールのリーダー。マッチョとクイーンビーというそうだが、当然そいつらに差別されるお絵かきやらパソコンやら読書の好きな大人しい連中もいて、ナードと呼ばれる。アメリカの青春コメディでは、このマッチョ対ナードというシチュエーションがよく登場する。映像製作の道に進むのはだいたいナードな奴だから、コメディではマッチョが散々バカにされるわけだ。
「でかけりゃいいってもんじゃないだろう」と言いたくなるが、科学の世界には大きいほど性能が向上する観測機器が存在する。天体望遠鏡だ。
口径が大きいほど、沢山の光を集めることができるので、より暗い星を観察することができる。また口径が大きいほど、分解能が良くなる。つまりより細かいところがはっきりと見えるようになる。天体望遠鏡にとって「大きいは正義」なのだ。
天体望遠鏡の歴史は、巨大化に伴う技術的問題の解決と、更なる巨大化の繰り返しだ。望遠鏡が巨大になるほどに、我々はより深く宇宙を知ることができるようになっていく。
人間の瞳は口径7mmほどだ。それに対してガリレオ・ガリレイ(1564〜1642)の最初の望遠鏡は対物レンズの口径が16mm。後に38mmと58mmの望遠鏡も製作した。この時代の望遠鏡の問題点は色収差だった。光の波長によって屈折率が変化するので、像が虹色にぼけるのである。色収差は口径が大きいほどに大きくなる。大口径にしてもより鮮明な画像を得るというわけにはいかない。同じ口径の場合、焦点距離が長いほど、色収差は小さくなる。
というわけで、ガリレオのあとしばらくは口径の割に思いきり焦点が長い空気望遠鏡というものが使われた。クリスティアン・ホイヘンス(1629〜1695)が土星の観測に使った望遠鏡は、口径220mmで焦点距離が64mもあった。あまりに長いので、対物レンズと接眼レンズを結ぶ鏡筒がなく、間に張ったワイヤで対物レンズの向きを操作する。だから空気望遠鏡というわけだ。
レンズの代わりに凹面の反射鏡を使えば、色収差は出ない。というわけで、ジェームズ・グレゴリー(1638〜1675)が考案してアイザック・ニュートン(1642〜1727)が改良したのが反射望遠鏡だ。ニュートンの製作した反射望遠鏡は口径2インチ(50.8mm)、銅とスズの合金を磨いた反射鏡を使っていた。反射鏡によって色収差を克服した望遠鏡は、巨大化を開始する。天王星の発見者でもあるウィリアム・ハーシェル(1738〜1822)は練達の反射鏡研磨職人でもあり、次々に大型の望遠鏡を作っていった。彼の手による最大の望遠鏡、通称「40フィート望遠鏡」は口径49.5インチ(126cm)もあった。40フィート(12.2m)というのは主鏡の焦点距離である。ただし、この望遠鏡は使い勝手が悪かったので、ハーシェルはより小さな「20フィート望遠鏡」を好んで使用した。こちらは口径が12インチ(30.5cm)だった。
合金製の反射鏡は反射率が低く、またすぐに表面が酸化して曇るので、頻繁に研磨する必要があった。ハーシェルは鏡の研磨を行えたからこそ、大型の望遠鏡を使いこなすことができたのだろう。
レンズを使う屈折望遠鏡には色収差が発生するが、人間の目では色収差が発生しない。眼球を解剖すると、様々な質感の部分が組み合わさっている。すなわち様々な種類のガラスを組み合わせれば色収差を消すことができるのではないか――ということはニュートンの時代から広く知られた推測だった。この推測に従い、イギリスの弁護士でアマチュア天文家でもあったチェスター・ムーア・ホール(1703〜1771)は試行錯誤を重ねて1730年頃、2種類のガラスを組み合わせて色収差を取り除く技術を完成させた。アクロマートレンズ(色消しレンズ)だ。やがてアクロマートレンズの製法はいつの間にか眼鏡職人の間に拡がり、ロンドンの眼鏡職人ジョン・ドロンド(1706〜1761)が1752年に工業的にアクロマートレンズの製造販売を始めた。アクロマートレンズは合金製反射鏡よりも光を有効に集めたので、同じ口径ならより暗い星を観測することができる。また、曇りをとるための研磨も不要だ。
かくして、再度屈折望遠鏡の時代が到来する。軍事的にも砲術のために観測用光学機器の需要が増えた、あるいはドイツに光学ガラスの天才ヨーゼフ・フォン・フラウンフォーフェル(1787〜1826)が現れて光学ガラスの性能を飛躍的に高めたなどの事情も重なり、19世紀を通じて、屈折望遠鏡の最盛期となる。
で、このあたりから「甘い、脂っこい、でかい」のアメリカ人が、「でっかい望遠鏡」の分野に参入してくる。今回紹介する「パロマーの巨人望遠鏡」は、パロマー天文台の200インチ(5m)望遠鏡を中心にすえた、アメリカの巨大望遠鏡建設の記録である。
19世紀アメリカの資本主義は、今からは考えられないほど猛悪なものだった。現在のような不公正を防ぐ制度が整備されているわけではない。多少不公正な手段を使おうともやったもん勝ち、というわけで、19世紀後半のアメリカでは経済発展も相まって、従来とは桁の違う規模の金持ちが出現するようになった。
シカゴの鉄道王チャールズ・ヤーキース(1837〜1905)もそんな桁外れの金持ちの一人だった。フィラデルフィアの片田舎に生まれ、穀物投機で得た資金を鉄道に注ぎ込み、ついには鉄道王とまで言われるようになったが、その過程はといえば贈賄と恐喝の連続。評判は極めて悪かった。
どんな悪人でも財を成すと次には名誉を求める。ヤーキースもまた、名誉を求めた。そこに近づいたのが天文学者のジョージ・エラリー・ヘール(1868〜1938)だ。彼はヤーキース主催の晩餐会に潜り込み、巨大望遠鏡建設の意義を説いた。
「ヘールはまったく知らなかったのだが、ヤーキス(原文ママ)は少年の頃から最大の望遠鏡を作ることを夢見ていたと、きまり悪そうにヘールに打ち明けたのであった。」(本書上巻p.44)
このエピソードが本当かどうかは分からないが、とにかく「でかい」ということがヤーキースの興味を引いたことは確かなようだ。
ヘールは、ヤーキースから提供された資金を使って、1897年に巨大な屈折望遠鏡を持つ天文台を完成させた。その名をヤーキース天文台という。屈折望遠鏡の口径は40インチ(102cm)。現存する世界最大の屈折望遠鏡である。この望遠鏡は、その後長く、年周視差による恒星までの距離の測定に使われることとなった。
ところが、ヘールはここで止まらなかった。
口径1mものレンズとなると、その製造は非常に難しくなる。まず、そんな巨大なガラス素材をひずみなく鋳込むのも大変な作業だ。次に、反射鏡なら表面1面だけを磨けばいいが、レンズは表裏二面を研磨する必要がある。アクロマートレンズならレンズ2枚で4面だ。もっと精密に色収差を減らしたアポクロマートレンズは3枚構成だから6面の研磨が必要になる。また、レンズ面を通過する際に、4〜5%程度の光の損失が発生する。表裏2面だけならともかく、6面も透過するとその損失は無視できなくなる(現在の写真用レンズは、コーティング技術で損失を低減している)。
ここで、反射望遠鏡が復活する。19世紀を通して発達を続けた化学工業が、19世紀末には、ガラス面に銀をメッキすることを可能にしたのである。銀メッキ鏡は合金鏡より効率よく光を反射する上に、合金鏡ほどは保守の手間がかからない。濁れば薬剤で銀を洗い落として再メッキすればいい。こうなると、一面だけ研磨すればよい反射望遠鏡のほうが大型化には有利となる。後には、より反射率の良いアルミニウムを鏡面に真空蒸着する技術が開発され、反射望遠鏡の優位性は決定的となった。
ヘールの実家もまたエレベーター製造で財を成した大金持ちであった。ヤーキースの40インチ屈折望遠鏡完成の前年、ヘールの父、ウィリアム・ヘールは息子にひとつのプレゼントをした。直径60インチ(1.5m)の反射鏡用ガラス素材である。どう考えても、ヘールパパが「息子にもっとでかい望遠鏡を」とヤーキースに対抗した結果と思えるのだが、ともかくこの素材は「より大きな望遠鏡を」というヘールの野望に火を付けたようである。
ヤーキースの次にパトロンとなったのは、鉄鋼王アンドリュー・カーネギー(1835〜1919)だった。タイミングの良いことに、カーネギーは1902年に科学振興を目的としたワシントン・カーネギー協会を設立しており、いくらかの紆余曲折はあったものの、割合すんなりとヘールの巨大望遠鏡建設計画に資金を提供した。そこでヘールは、父からもらった60インチのガラス素材で製造した反射鏡を持つ望遠鏡を、カリフォルニア州パサデナの郊外、ウィルソン山山頂に建設した天文台に据え付けた。ヘール父にちなんでヘール望遠鏡と命名されたこの望遠鏡は1908年から稼働を開始し、遠い銀河の分光観測などに多大の成果を挙げることとなった。
そのまま、ヘールはより巨大な望遠鏡の建設に突進する。今度はカーネギーに加えて、ジョン・D・フッカーというロサンゼルスの資産家が多額の資金を提供した。望遠鏡の口径は当初84インチ(2.13m)を想定していたが、フッカーはヘールにもっと大きくしようと提案した。「金なら出すから100インチ(2.5m)にしよう(Make it 100-inches and I shall pay for it.)」。
1917年、ウィルソン山天文台の100インチ望遠鏡が完成する。フッカー望遠鏡と命名されたこの望遠鏡を駆使してエドウィン・ハッブル(1889〜1953)は、遠方の銀河の赤方偏移を観測し、宇宙が膨張していることを示した。
まだまだヘールは止まらない。100インチの次は200インチ(5m)だ。パトロンとなったのは、石油王ジョン・ロックフェラー(1839〜1937)が1913年に設立した慈善団体のロックフェラー財団である。
200インチ望遠鏡の建設は、文字通りの苦難の道だった。寸法が2倍ということは面積は4倍、体積と重量は8倍になるということだ。巨大なガラスの鋳込みも、研磨も、重くなった望遠鏡を支える架台の設計も、すべては未知の領域にあった。
巨大なシステムが内包する難題を、いかにもアメリカ的な「合理的な力づく」で突破しながら、望遠鏡の開発は進んでいく。だが犠牲も大きい。山積する問題をひとつ解決するたびに、誰かが命を使い尽くして死んでいくのである。ヘールもまた、1938年に69歳で力尽きる。
第二次世界大戦を挟んで、1948年、カリフォルニア州サンディエゴのパロマー山にて、200インチの巨大望遠鏡は稼働を開始した。この望遠鏡もまたヘール望遠鏡と命名された。もちろん、このヘールはジョージ・エラリー・ヘールその人である。
この本の主役は人ではない。巨大な望遠鏡そのものである。人々の人生を飲み込み、砕き、絞り取り、望遠鏡は完成に近づいていく。
柴田錬三郎に、江戸城そのものを主役にすえた『嗚呼 江戸城』(文藝春秋社)という小説がある。ノンフィクションの本書とシバレンの大河小説は、意外なほど読後感が似ている。城のように、巨大望遠鏡は個人の人生を超えて屹立する存在なのである。
ヤーキース40インチからパロマー200インチに至るまでのヘールが建設した巨大望遠鏡が天文学にもたらした成果は巨大だ。アメリカ人の「でかいの大好き」が、これほどポジティブに結果を生んだ例はほかにそうはないだろう。
その後1974年に、アメリカ人以上に「でかいの大好き」なロシア人がコーカサスのゼレンチュクスカヤに口径6mの望遠鏡「BTA-6」を完成させたが、鏡面精度や架台の制御に問題があってはかばかしい成果を挙げることができなかった。
次のブレイクスルーは、鏡面のコンピューター制御と、適応光学系による大気のゆらぎの補正、そして分割鏡の実用化だろう。これらの技術により、パロマーの200インチを超える巨大望遠鏡の建設が可能になった。現在、口径21.4mの「ジャイアント・マゼラン望遠鏡」がチリ・ラスカンパナスに建設中だ。口径30mの望遠鏡「TMT」もハワイ・マウナケア山での建設がほぼ確定した。その先にはより巨大な望遠鏡の構想も動き出しつつある。
人間は知的好奇心が満足するまで、より巨大な望遠鏡の建設をやめないのだろう。では、どこまでいったら満足するのか――それは誰にも分からない。
【今回ご紹介した書籍】
『パロマーの巨人望遠鏡(上)(下)』
デヴィット・O・ウッドベリー 著/関 正雄,湯澤 博,成相恭二 訳
(上)354頁/定価1012円(本体920円+税10%)/2002年6月発行/ISBN9784003394212
https://www.iwanami.co.jp/book/b247064.html
(下)350頁/定価946円(本体860円+税10%)/2002年7月発行/ISBN9784003394229
https://www.iwanami.co.jp/book/b247065.html
岩波文庫
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2012
Shokabo-News No. 282(2012-12)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.日経BP社記者を経てフリーに.現在,PC Onlineに「人と技術と情報の界面を探る」を連載中.主著に『われらの有人宇宙船』(裳華房),『増補 スペースシャトルの落日』(ちくま文庫),『恐るべき旅路』(朝日新聞出版),『コダワリ人のおもちゃ箱』(エクスナレッジ),『のりもの進化論』(太田出版)などがある.ブログ「松浦晋也のL/D」
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(偶数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 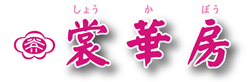
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム