第2回 使われている技術はその目的に最適なのか?
『20世紀のエンジン史』(鈴木 孝 著,三樹書房)
 私たちの生活は、多くの科学と技術の成果によって支えられている。衣食住のすべて、情報の伝達手段、コミュニケーション手法、天気予報のような自然の観察と予測、医療などなど、科学技術の成果でないものを探す方が難しい。
私たちの生活は、多くの科学と技術の成果によって支えられている。衣食住のすべて、情報の伝達手段、コミュニケーション手法、天気予報のような自然の観察と予測、医療などなど、科学技術の成果でないものを探す方が難しい。
ところで、科学と技術の違いがどこにあるかご存じだろうか。科学は自然に対する知識の蓄積であり、技術はその応用である。二つは関連しつつも様々な面で異なるが、一番の違いは「科学の答えは一つであるのに対して、技術の解は複数存在しうる」ということだ。
科学による自然現象の把握は、時代によって変化し、深化していく。いくつかの説の並立はやがてより現実を的確に説明できる一つの考え方に収斂する。次により的確に現象を説明できる説が現れれば同じプロセスを経て新しい考えが古い考えにとって変わる。
燃焼という現象を例にとろう。古代ギリシャの哲学者アリストテレス(B.C.384〜B.C.322)は四原質と四性質で世界を説明できると考えた。四原質とは、土、水、空気、火であり、四性質とは乾、湿、温、冷だ。四原質はそれぞれ四性質の二つを持つ。土は乾・冷、水は湿・冷、空気は湿・温、火は乾・温となる。火は原質として物質的実態があるものとして捉えられている。
17世紀に入り、錬金術師ヨハン・ベッヒャー(1635〜1682)は、アリストテレスのいうような四原質だけではなく、“燃える土”という原質が存在すると考えた。燃える土は燃える物質すべてに含まれていて燃焼とは燃える土が抜けていく過程のことだと考えたのである。ベッヒャーの考えは医師のゲオルク・エルンスト・シュタール(1660〜1734)に引き継がれた。シュタールは“燃える土”に「フロギストン(燃素)」という名前を与えた。
18世紀前半の欧州ではフロギストン説は主流となった。多くの物質は燃えると灰になり、体積は縮む。だから燃える物質はすべてフロギストンを含んでいて、燃焼とはフロギストンが抜けることだ、という説明はきわめて自然に思えたのである。しかしながら、様々な物質を片っ端から燃やしていくとフロギストン説とは矛盾する結果が得られることが分かってきた。特に、金属類を燃やすと燃やす前よりも重くなるという現象はフロギストン説にとっては都合が悪かった。フロギストンが抜けるからには残る灰は軽くならねばならないはずなのだ。
「燃焼とは何か」という問題に決着をつけたのは、アントワーヌ・ラヴォアジエ(1743〜1794)だった。彼は密閉した容器中で金属を燃焼させ、燃焼の前後で質量が変化しないことを示した。さらに、燃焼後の容器を開けると、外側から内側に空気が流入することを発見した。つまり、燃焼とは空気中に含まれる何らかの物質が金属と結合する反応なのだ。さらに彼は、イギリスの神学者ジョゼフ・プリーストリー(1733〜1804)から水銀を燃やした後の灰を強く加熱すると気体が出てくること、その気体は燃焼を激しくする効果があることを聞いた。ラヴォアジェはプリーストリーの得た気体こそが燃焼のキモであって、燃焼とはこの気体が様々な物質と結合する反応のことではないかと気がつく。1779年、ラヴォアジェはこの気体に「酸素」という名前を与えた。プリーストリーの実験は、水銀を燃やした結果生成した酸化水銀を加熱して、酸素ガスを得るというものだったわけだ。ラヴォアジェの洞察は、その後の数年で様々な反論への再反論と補強の実験を経て確たる事実として確立していった。
このように、科学においては様々な仮説が入り乱れ、自らの正しさを主張する中から実験により事実と合わない仮説が淘汰され、最終的に誰もが納得できる説が事実として認められる。どんなに確立した定説であっても、さらなる実験で矛盾が見つかれば、もういちど仮説に戻って再検討を行う。仮説は並立するが、事実と認められる説は一つだ。
が、これが技術となると話は違ってくる。燃焼から有用なエネルギーを取り出す仕組みひとつをとっても様々な方式が併存しうるし、実際に適材適所で使い分けられる。答えはひとつではないのだ。
最初の実用的な蒸気機関、トーマス・ニューコメン(1664〜1729)が発明したニューコメン機関がどんなものかご存じだろうか。まずピストンを引いて水蒸気をシリンダーに吸い込む。ついでシリンダーに水を吹き込む。すると水蒸気が液化して圧力が下がるのでピストンがぐっと下がる。この動きをピストンにつながったロッドの往復運動として取り出して、つるべ井戸の方法で水をくみ上げる。つまり、私たちの知る「高圧蒸気でピストンを押す」蒸気機関とは全く正反対の「蒸気の液化で体積が減って負圧が発生する」ことを利用していたのだった。材料技術が未発達で、高圧水蒸気を使うとシリンダーが破裂してしまうので、このような方法を採用したのである。
ニューコメン機関は高温の水蒸気に直接シリンダー内で水を吹き込んで冷やしている。するとシリンダーそのものも冷えてしまい効率が悪い。そこでジェームズ・ワット(1736〜1819)は水蒸気を別の部屋に導いてから冷却する「復水器」という仕組みを発明した。ワットはほかにも様々な工夫をこらして近代的な蒸気機関の基本形を作り上げることに成功する。その後鋼材の技術や溶接やリベット止めなどの手法が発達したことから、より高温高圧で効率のよい蒸気機関も作れるようになった。
が、別にピストン式の蒸気機関だけが燃焼からエネルギーを取り出す仕組みではない。
1816年、スコットランドの牧師ロバート・スターリング(1790〜1878)はスターリングエンジンを発明した。蒸気機関と同じく外燃機関、つまり動作流体の外側で燃焼が起きている機関だが、蒸気機関と全く動作原理が異なり、熱的な効率が高いという特徴を持つ。また、高圧水蒸気を羽根車にあてて回転させる蒸気タービンは、1884年にチャールズ・アルジャーノン・パーソンズ(1854〜1931)によって発明された。
動作流体内で燃焼を行う内燃機関は、18世紀から試作が行われていたが、ニコラ・カルノー(1796〜1832)が1824年に論文「火の動力」を公表し、熱力学の基本を定式化したことで理論的検討が可能になり、研究が進展した。1876年には、ニコラウス・オットー(1832〜1891)が4サイクルエンジンを発明。1879年にはカール・ベンツ(1844〜1929)が2サイクルエンジンを発明。1893年にはルドルフ・ディーゼル(1858〜1913)がディーゼルエンジンを発明。本格的な内燃機関の時代が始まった。
注目すべきは、内燃機関が出現したからといって蒸気機関をはじめとした外燃機関が消えたというわけではないことだ。また、それぞれのエンジン形式も開発者の工夫によって様々な構造の差異が存在する。どの方式がどの分野で生き残るかは、最終的には経済性の問題に帰着する。
ダイナミックな論争と適切な観測と実験を経てひとつの説へと収斂していく科学に対して、技術は適用分野、材料など周辺技術の進捗状況、さらには社会状況などに影響され、最適解は変化し続ける。たいていの場合は、一つに収斂することはないし、収斂した場合も、状況が変化すればすぐに様々な新技術が出現して利便性を競うことになる。
このため、技術の歴史には、そこには様々な“行き止まり”が存在する。開発当時は前途洋々に思われたものの、見込み違いや周辺技術の進歩、社会状況の変化などによって消えてしまった技術が多々あるのだ。が、それらは無駄というわけではない。消えた技術を知り、消えた理由を考えることは、今後の技術開発を考察するにあたって大変有益な知見をもたらしてくれる。
「20世紀のエンジン史 スリーブバルブと航空ディーゼルの興亡」は、それら消えた技術の中でも二つのエンジン技術、すなわちスリーブバルブと航空用ディーゼルエンジンについての解説書だ。内燃機関のそのまたごく一部の技術の話ということで、まさに重箱の隅をつつくような話が続くが、そのことがかえって、様々な状況に左右される社会のなかの技術全般のありようをはっきりと見せてくれる。
シリンダーとピストンを使う内燃機関ではシリンダー内に空気と燃料を吹き込み、点火する。発生した燃焼ガスでピストンを押し下げてエネルギーを取り出し、燃焼の終わったガスはシリンダーから排出する。だから吹き込み口と排出口は適切なタイミングで開閉を繰り返す必要がある。現在一般に使われているのはポペットバルブ(茸形弁)というものだ。茸のかさのように広がったバルブで、茸の柄にあたる部分(ステム)がカムなどに押されて、かさの縁の部分がガスの吹き込み口や排出口の縁と密着したり離れたりしてガスの流れを制
御する。ところがこの方式だと、バルブと吸排気口とが、がちがちと高速でぶつかるわけで20世紀初頭の段階では気密性や耐久性の確保が大変大きな課題だった。
そこで出現したのがスリーブバルブだ。スリーブ(洋服の袖)の名の通り、この方式ではピストンとシリンダーの間にもうひとつ、スリーブという薄い金属の円筒が入る。スリーブはカムによってピストンとは別のタイミングで上下運動する。スリーブには穴が開いていてシリンダー側に開いた吸排気口とスリーブの穴が重なった時だけ、燃料を含む空気がシリンダーに入ったり燃焼済みガスが排出されたりする。
スリーブバルブは、第二次世界大戦前に、有望な形式として自動車から航空機に至るまでの幅広い用途で使用された。とはいえ、問題がないわけではなかった。この形式を採用したエンジンのシリンダー内では、入れ子になったピストンとスリーブがそれぞれ異なる上下運動をする。確かにポペットバルブのようにがちがちとぶつかる部分がなくなるが、その一方でこすれ合うピストン、スリーブとシリンダーの摩擦をどう軽減するかとか、スリーブとシリンダー間の気密をどうやって保つかとかの、別の問題が浮上する。まして、初期のスリーブバルブ方式は開口と閉口のタイミングを最適化するためにスリーブを二重にしていた。ピストン、内側スリーブ、外側スリーブという組み合わせがシリンダーの内側でそれぞれ別の上下運動をするわけで、複雑きわまりない。
本書は、そんなスリーブバルブ方式の発展を、ていねいに追っていく。スリーブは巧妙な工夫で一つだけで済むようになる。やがてイギリスでは、ロイ・フェッデン(1885〜1973)という技術者が現れ、粘り強い技術開発を何年も継続して行った結果、ついにスリーブバルブを採用した航空機用エンジンの傑作、ブリストル・セントラースが完成する。第二次世界大戦後期になって量産体制が整ったセントラースエンジンは、ホーカー・テンペスト戦闘機に採用されて航空戦での勝利に貢献することになった。
本書が解説する、セントラースに込められた工夫の数々には感嘆するしかない。ほとんど芸術品だ。ところが、セントラースを最後に、スリーブバルブはエンジン技術の表舞台から姿を消してしまう。一番大きな理由は、航空機用エンジンの主力がジェットエンジンに移行したことだったが、なぜ自動車用などでスリーブバルブは生き残れなかったのか。自動車用エンジン技術者の著者は、スリーブバルブは技術開発の寄り道だったと総括する。フェッデンのような優れた技術者が長期間にわたって努力した結果、実用レベルに到達したが、それは本当に必要な努力だったのか、と。技術的難易度をポペットバルブ方式と比べるとむしろ難しいぐらいで、得られる利点もそんなに大きくなかったというのだ。
本書後半では、第二世界大戦時にドイツが実用化し各国が追従して開発に動いた航空機用ディーゼルエンジンに話題が移る。こちらもスリーブバルブ同様消えてしまうのだが、話は鉄道用ディーゼルエンジンや、著者の本業であるトラック用ディーゼルエンジンなどにもおよび、燃焼工学や機械構造の解説も含めて、より幅広く失敗の分析を行っている。
今回、科学と技術の違いから入って、実用化されたが消えた技術をみてきた。このようなことを書く理由は、私が原子炉について同様の疑問を持っているからだ。福島第一原子力発電所で事故を起こした原子炉は、アメリカが開発した軽水炉、それも沸騰水型の原子炉だった。では、この軽水炉・沸騰水型という形式は、本当に民生用・発電用に最適の炉形式だったのだろうか。それともなにかの弾みでたまたま実用化してしまい、技術的合理性ではなく社会的理由から普及してしまった形式なのだろうか。
原子炉開発の歴史には2人のキーパーソンが登場する。一人はアメリカ海軍で原子力潜水艦と原子力空母の開発に執念を燃やしたハイマン・リッコーヴァー(1898〜1986)、もうひとりは原子力工学の研究者で、アメリカの原子炉研究の中枢であるオークリッジ国立研究所の所長を長年勤めたアルヴィン・ワインバーグ(1915〜2006)。軽水炉という炉形式は、船舶に最適としてワインバーグがリッコーヴァーに提案したものだった。海軍の資金で軽水炉の開発は進み、やがてそのままアメリカ初の原子力発電所である、シッピングポート原子力発電所(ペンシルバニア州)に転用される。ところが、提案者であるワインバーグはオークリッジの所長時代に、民間用原子炉としてトリウム溶融塩炉という軽水炉と別の形式の原子炉開発に没頭した。
トリウム溶融塩炉の開発は途絶し、今、世界ではもともと原子力潜水艦のために開発された軽水炉が大量の電力を供給している。しかし、軽水炉はそもそも民間で使うにあたって最適の炉形式だったのか、それとももっと安全で扱いやすい別の炉形式が存在し得たのか。
あり得たかもしれないもうひとつの技術――スリーブバルブと航空用ディーゼルエンジンの例は興味深い視点を提供してくれている。
【今回ご紹介した書籍】
『20世紀のエンジン史 スリーブバルブと航空ディーゼルの興亡』
鈴木 孝 著/四六判/468頁/定価2640円(本体2400円+税10%)/2001年12月発行/
ISBN978-4-89522-283-9/三樹書房
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2012
Shokabo-News No. 276(2012-6-28)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター.1962年東京都出身.日経BP社記者を経てフリーに.現在,PC Onlineに「人と技術と情報の界面を探る」を連載中.主著に『われらの有人宇宙船』(裳華房),『増補 スペースシャトルの落日』(ちくま文庫),『恐るべき旅路』(朝日新聞出版),『コダワリ人のおもちゃ箱』(エクスナレッジ)などがある.ブログ「松浦晋也のL/D」
※「松浦晋也の“読書ノート”」は,裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月(偶数月予定)に連載しています.Webサイトにはメールマガジン配信の約1か月後に掲載します.是非メールマガジンにご登録ください.
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 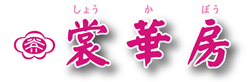
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム