第59回 “殿様”と右翼と左翼
『最後の殿様 −徳川義親自伝』(徳川義親 著、講談社、1973年刊)
さて第57回の続き。「中国大陸で日本が行った阿片密売の上がりは、戦後政治にいかにして流れ込んだのか」という問題意識で読書をしていたら、興味深い人物が次々に網に引っかかってきてしまったという流れで行き当たったのが、今回取り上げる『最後の殿様』だ。
これがもう滅茶苦茶に面白い本で、今回の原稿は引用だらけにならないように注意しないといけない……とまず自戒しないといけないぐらいだった。
“最後の殿様”徳川義親(とくがわ・よしちか、1886〜1976)とはどんな人物か。華族であり貴族院議員でもある。89歳まで長生きし、幕末大名の息子としては最後まで健在だったので、「最後の殿様」と呼ばれた。
その父は幕末に幕府の重臣を務め、大政奉還で大きな働きをした“幕末四賢侯”のひとり松平春嶽(1828〜1890)。義親は明治になってからの、春嶽晩年の子どもだ。妾腹に生まれ、実母を「おかあさん」とは呼べぬ環境で成長。幼少期の回想として描写される明治の旧大名家の生活・しつけだけでも十分に面白い。
後に尾張徳川家に養子として入り、尾張徳川家第19代当主となった。
東京帝国大学国史科を幕府期の木曾林政史の研究で卒業。ただし成績はビリ。歴史の研究はつまらないと生物科に入り直してイチョウの精子の研究に没頭し、今度は首席で卒業後、自宅に植物研究所をつくる。
そのままいかにも華族さまっぽい研究三昧の生活に入ると思いきや、マレー半島のスルタンと親しく交わり、猟で虎を仕留めて「虎狩りの殿様」と有名になる。さらに、右翼左翼ごったまぜで交友を深め、昭和のクーデター未遂事件の三月事件(1931年3月)、十月事件(同年10月)にはクーデター資金を提供するなどして、昭和の政治にフィクサーとして関わっていくのである。
本書を読む限り、義親はバカ殿でも、偉ぶった華族でもなかった。本書の文章を直接本人が書いたのか、それともインタビューをゴーストライターが文章に仕立てたのかは不明だが、本書に一貫するのは、徳川義親という人の精神が宿す風通しの良さである。
それは合理性といってもいい。情念で湿っぽくぬめるところがなく、常に合理的で理が立っている。しかも理だけで人間心理の綾を無視しているのかというとそうでもない。人間関係を理で分析し、理解した上で人と接していくのだ。本書には彼が接した様々な人々の分析が出てくるが、そこには偏見がなく、しかも遠慮もない。ダメなところはダメと言いつつ、同時に「ダメなところもあるのも人間というものだ」と鷹揚に構えて、決して感情的に排除したり非難したりすることなく、付き合いを続けていく。
その付き合いは多彩だ。三月事件、十月事件の首謀者である陸軍軍人の橋本欣五郎(1890〜1957)、大アジア主義の理論的支柱の大川周明(1886〜1957)、東京毎日新聞社社長にして上海の青幇とも通じた麻薬フィクサーの藤田勇(1887〜没年不詳)、歴史のあちこちに顔を出す右翼活動家の清水行之助(1895〜1981)、陸軍軍人の長勇(1895〜1945)といった、第57回で取り上げた『特務機関長許斐氏利』にも登場した右翼人脈が登場するかと思うと、社会主義者の石川三四郎(1876〜1956)、アナーキストの吉田一(1892〜1966)、敗戦後に日本社会党の立ち上げに尽力して後に同党委員長を務めた鈴木茂三郎(1893〜1970)といった左翼活動家の面々とも親しく交遊し、支援する。
なぜ徳川の血を引く華族がそんなことができたのかといえば、「そもそも天皇に主権があるとした明治憲法は、薩摩と長州がすべての責任を天皇に押しつけて自分達が無責任な形で好き勝手するために作ったものだ」という物の見方をしていたからである。いかにも旧幕府側の明治憲法観である。が、明治憲法の天皇主権という根本原理には、統帥権干犯という深刻かつ致命的なバグが存在したことを考えれば、これは正しいものの見方でもある。
「すべての権力を天皇に押しつければ、すべてが天皇の責任になる。しかし、すべてを天皇の責任にすれば、政治は天皇の権威を笠に着る利権漁りの場にならざるを得ない。実際大正以降の政党政治はそうなっていったではないか」というわけだ。「いずれ天皇は象徴にせざるを得ない。国家運営の責任は政治が持たねばならない。そのためには貴族院の改革が必要だ」と、彼は貴族院議員の立場を利用して政治的に動き始める。
その貴族院改革案がなかなか面白い。彼は普通選挙を「選挙区で選ばれた政治家が、選挙区の住民すべての利益を代表できるか、できるはずがない。選挙区を区切って選挙を行えば必ず切り捨てられる者が発生する」と考える。そこで、貴族院を職能別の議員で再構成する。つまり農民、漁民、鉱山労働者、工場労働者、都市生活者などの職業別に議員を割り当ててその代表を出して一院を立てるというのだ。その上で選挙区選出の衆議院とかみ合わせて、すべての国民の利益を代表する者が集まって国政を議論する場をつくり出そうとしたのであった。しかし、彼の貴族院改革案は一顧だにされず、挫折する。
そんな彼のところに、社会改革を志向する者らが、集まってくる。そんな者らを、彼は左右の区別なく受け入れて援助する。右とか左とかの立場の違いは、単なる方法論の違いであって、共に今の社会を良くすることを目指すという意味では同じではないか、と考えたのだ。
そして──これがいかにも明治から昭和前期という時代であり、幕末の殿様を父に持つ者の思考だと思うのだが──彼は、大日本帝国の政体が絶対だなどと、微塵も考えていない。天皇主権、天皇絶対といっても、それは薩長のつくった虚構に過ぎない。よりよい理想の社会をつくるためなら、暴力で潰してもいいのである。それ故、彼は普通選挙法と抱き合わせで成立した治安維持法に、強く反対する。
少数特権階級の政治は、かならず国民大衆の反感を買うものである。この政治の根本的姿勢を改めないで、このような法律で取り締まると、必ず警察官横暴になって、国民の言論、集会、結社の自由を破壊して、穏健な国民までも弾圧するようになり、かえって国家を危険に突き落とすことになる。 (本書 p.107)。
最晩年の回想なので、話を盛っているかもと思い、普選法の成立した大正14年(1924年)貴族院議事録を検索したら、確かに彼はかなり激烈な調子の治安維持法反対の論陣を張っていた。
https://teikokugikai-i.ndl.go.jp/#/detailPDF?minId=005003242X02519250319&page=32&spkNum=51¤t=7
昭和に入ると徳川義親は、クーデター計画に資金を提供するパトロンとなる。そこにも彼独特、かつ時代なりの暴力に肯定的な、しかしながら今から見ても透徹した思考と洞察が存在する。
あまり国民に不満を溜めると、共産革命が起きて日本は共産国家になってしまう。それを避けるためには、機先を制してクーデターを起こし、現状の政治腐敗を一掃しないといけない。だから彼は橋本欣五郎らの三月事件にぽんとカネを出した。
三月事件は陸軍を中心にしたクーデター計画だったが、計画に加わった大川周明らは、無産政党、つまり左翼にも手を回して同時多発的に東京に争乱を起こす手筈を整えていた。このあたり右とか左とかの政治思想で区分しては事を見誤る。むしろ幕藩体制の延長としての大日本帝国と、共産主義や国家社会主義(ファシズム)といった20世紀の政治思潮との衝突と見たほうがいい。
そして共産主義とファシズムは、右と左という対立する政治思想ではなく、権力の集中による国家運営の効率化という点で大変親和性が良い。共産主義者もファシストも、社会を暴力的に改革するという点では一致していたのである。
三月事件は、一度はクーデターを承知した宇垣一成陸軍大臣が、ぎりぎりになって翻意したために実行に移すことなく収束した。徳川義親は一転して、事を穏便かつ秘密裏に収めるために奔走する。橋本欣五郎は満洲事変直後の1931年10月に再度クーデターへと動くが、今度は内部に密告者が発生して失敗した。橋本はその後、1957年の死に至るまで政治的な活動を続けたが、義親によれば2回の挫折の経験から「我が国では、軍隊を使ったクーデターは成功しない」と結論していたという。
10月事件から4年半後の1936年、二・二六事件が発生する。徳川義親は、三月事件、十月事件、さらに1932年の五・一五事件の理論的支柱となった大川周明と、二・二六事件で同じ立場となった北一輝(1883〜1937)を比較し、大川を高く評価する。
大川くんは真っ正直で、生活費は自分の働きでまかなう。革命資金を受け取ればきちんと会計報告をする。(中略)交際範囲も広く、共産党員でも抱擁していく。
北くんは革命一本槍だが、幅がせまく交際範囲もうすい。自分で働かないので、人を脅かすようにして金を出させたりもする。
(本書 p.139〜140)
労働と会計から人品を推し量る──この殿様、徹底したリアリストなのである。
二・二六事件の時も、徳川義親はリアリストの側面を存分に発揮する。事件発生当日、状況は混乱しており、誰にアクセスすれば事を収めることができるのか見当もつかない。義親は「大川くんに頼るしかない」と考える。改革派軍人に広く人脈を持つ大川周明なら、どこの誰が何を考えているかが分かる。誰を説得すれば事が収まるかが分かる。ところがこの時、大川は五・一五事件の罪で服役中だった。
義親は小原直司法大臣に面会し、病気名目で一時大川を釈放しろと迫る。難色を示していた小原は、交換条件に、大川主宰の政治団体である神武会の解散を要求した。このあたり、法の秩序を越えた見事なくらいの人治の思考であり、人治のやり取りである。
神武会は、天皇中心の国体は護持したままの政治改革を標榜して、過激な活動を続けていた。当時の政府は神武会を共産党と並ぶ危険政治団体と認識していたが、国体護持を掲げているので治安維持法の取締対象にはならず、警察では取り締まることができなかったのである。
徳川義親はその要求を呑み、大川は聖路加病院に移された。大川の指示で、叛乱軍鎮圧の命令を受けて、千葉県佐倉から上京した陸軍歩兵第五十七連隊の山口直人連隊長に使者が走る。五十七連隊が叛乱軍側に付くか否かでクーデターの帰趨が決まると読んでのことだった。山口連隊長が叛乱軍側に付かないと明言したことで、二・二六事件の失敗は決定した。
その上で、徳川は大川とともに叛乱軍側のキーパーソンと面会し、「お前らの気持ちは良く分かるから、必ずこの徳川が天皇陛下に伝える。その代わりお前らは責任を取って腹を切れ」と、誰にも罪を被せないかたちで穏便に収拾しようとした。事件首謀者の切腹が穏便かどうかは、なかなか今の価値観で推し量れるものではないけれども。
が、2月28日に昭和天皇の反乱鎮定の奉勅命令が出たことで、一気に決起側は天皇に仇為す叛徒ということになり、徳川・大川の目論見は失敗する。
後に大川は、周囲の反対を押し切って神武会を解散した。一度約束したことは守る、ということであろう。こういう大川の生真面目さ・潔癖さを、徳川は評価していたようである。
後に徳川は「お前らの気持ちは必ず天皇陛下に伝えるといっても、徳川に叛乱側の意志を天皇に拝謁して伝える機会は作れなかったろう」と批判された。それに答えて曰く、「陛下は生物学者である。ぼくもまた生物学研究所を持っている。生物学を通じてならばいつでも拝謁の機会はあるし、お話もできる」(本書p.164)。まったくもう、あくまで実際的に考えるリアリストっぷりに恐れ入るばかりである。
1937年6月、盧溝橋事件をきっかけに日華事変が勃発し、日本と中華民国はなし崩し的に戦争を始めてしまう。同年11月に貴族院は慰問団を編成して、北支および華北に展開した陸軍を慰問訪問。徳川義親はこの慰問団に参加して、中国大陸を旅した。慰問団が上海に滞在していた時、徳川のところを藤田勇が訪れる。ここで徳川ははっきりと藤田が上海で何をしたのかを記述する。
藤田くんが上海に現れたのは、麻薬二十万ポンドを上海に密輸したあと始末にきたのである。麻薬は陸軍省に頼まれて、三井物産を通じ、イランから密輸した。二十万ポンドの麻薬はばくだいな量だが、陸軍はこれで戦争資金を調達するために、藤田くんに陸軍大臣の印鑑を押した注文書を発行した。 (本書 p.171)
この短い記述でいろいろなことがわかる。陸軍、それも出先の関東軍ではなく、陸軍大臣の印鑑を扱える東京の陸軍省が、中国大陸において、日本も批准している各種反阿片国際条約に違反する阿片密売を大々的に行って日華事変の軍資金を調達しようとしたこと。その違法行為を、三井物産および青幇にコネクションを持つ藤田勇という民間会社および民間人にやらせたことだ。
この仕事で藤田には、当時の金額で200万円もの巨額の手数料が入る約束になっていた。ところが陸軍が支払いを渋った。藤田は、橋本欣五郎や大川周明とつながっている。この金を元手にまたクーデターなど起こされてはたまらないと考えたのである。怒った藤田は、訴訟を起こして事を公然化するぞと陸軍に迫り、結局手数料20万円で手打ちにした。
関東軍および満洲国の意を受けて“阿片王”里見甫が上海にやってきて、三井物産および関東軍の力を使って阿片商社の宏済善堂を立ち上げたのが、同じ1937年11月である。この流れから、藤田に手を焼いた陸軍が、より従順な阿片流通事業者を求めて、中国人の間に人脈を拡げていた里見に白羽の矢を立てたらしいことがうかがえる。
ここまでの読書で、日本人による中国大陸での阿片流通は日露戦争後にまで遡り、かつ陸軍の裏金作りは第一次世界大戦の青島攻略あたりから始まることが分かっている。陸軍によるこのダーティワークは、連綿と続き、1937年の段階では関東軍の独断専行を越えて、陸軍省本体の管轄事項になっていたのである。それはおそらく、1938年12月の興亜院設立とともに、陸軍だけではない大日本帝国そのものの管轄となっていったのだろう。
阿片が生み出す巨大な利益は、最初大陸への日本からの移民が商い、そこに陸軍出先の関東軍が入り込み、傀儡国家の満洲国が依存し、東京の陸軍省が依存し、ついには大日本帝国そのものが依存するようになっていったのである。
1937年11月末に徳川義親は帰国する。が、藤田勇はその後も上海に留まり、阿片密輸の件の解決にあたった。12月のおそらくは半ば頃、南京攻略戦に参加した直後の長勇が藤田を訪問する。長と藤田は同じ福岡の出身。しかも十月事件で藤田は資金を提供し、長は橋本欣五郎麾下で動くという関係もあり、以前から二人は親しかった。長は、橋本を「親分」、藤田を「大親分」と呼んでいたという。
気安さ故か、長はとんでもない話を藤田にした。藤田はその話を徳川義親に伝え、義親は最晩年の回想録にその話を書き記した。
日本軍に包囲された南京城の一方から、揚子江沿いに女、子どもをまじえた市民の大軍が怒濤のように逃げていく。そのなかに多数の中国兵がまぎれこんでいる。中国兵をそのまま逃がしたのでは、あとで戦力に影響する。そこで前線で機関銃をすえている兵士に長中佐は、あれを撃てと命令した。中国兵がまぎれているとはいえ、逃げているのは市民であるから、さすがに兵士はちゅうちょして撃たなかった。それで長中佐は激怒して、
「人を殺すのはこうするんじゃ」
と、軍刀でその兵士を袈裟懸けに切り殺した。おどろいたほかの兵隊が、いっせいに機関銃を発射し、大殺戮となったという。長中佐が自慢げにこの話を藤田くんにしたので、藤田くんは驚いて、「長、その話だけはだれにもするなよ」と厳重に口どめしたという。
(本書 p.173)
この話に誇張が入り込むとしたら、長の肥大した自意識が自慢話として話を盛った場合だけだろう。その分を割り引くとしても、とてもではないが「南京大虐殺はまぼろしだった」などと言えない状況であったことが、このエピソードから見えてくる。
同時に、第57回の本コラムで見たように“任侠の人”であった長が、見事なくらいに戦略眼を欠如していたことも分かる。
そもそも日本が中国大陸に派兵した理由は何かといえば、表向きは中国大陸に秩序をもたらすためであり、実態は植民地支配のためであった。秩序の確立は植民地支配に不可欠であり、そのためには現地住民に対する人心収攬、最低でも人心安定が必須である。それを、逃げる兵もろとも一般市民を射殺すれば、多大な恨みを買って後々に禍根を残すに決まっている。
そんな簡単なことも長は理解できなかった。ただ、殺戮を己の武功と認識して藤田に対して自慢したのである。
【今回ご紹介した書籍】
●『最後の殿様 −徳川義親自伝』
徳川義親 著/四六判/232頁/定価680円/1973年刊/講談社
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2023
Shokabo-News No. 384(2023-2)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター。1962年東京都出身。現在、日経ビジネスオンライン「Viwes」「テクノトレンド」などに不定期出稿中。近著に『母さん、ごめん。2──50代独身男の介護奮闘記 グループホーム編』(日経BP社、2022年6月刊)がある。その他、『小惑星探査機「はやぶさ2」の挑戦』『はやぶさ2の真実』『飛べ!「はやぶさ」』『われらの有人宇宙船』『増補 スペースシャトルの落日』『恐るべき旅路』『のりもの進化論』など著書多数。
Twitterアカウント https://twitter.com/ShinyaMatsuura
※「松浦晋也の“読書ノート”」は、裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月に連載しています。Webサイトにはメールマガジン配信後になるべく早い時期に掲載する予定です。是非メールマガジンにご登録ください。
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 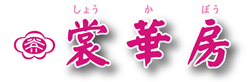
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム