��62��@���܂�Ɉَ��ł������O���
�w���{�O��x(�� �� ���A�����V���o�Łj
�@�����Ƒ����Ă������Ђ�����Ǐ������A���ݏ��X����Ă���B���ӎ��́u���a��������s��Ɏ���܂łɑ���{�鍑�����ۏ��Ɉᔽ���ď��������Ђ̎��v�́A���̓��{�̐����ɂǂ��W�����̂��v�����A���������o�ł���Ă���{�Ƃ��Ă͓ǂݐs���������ȁA�Ƃ����Ƃ���܂ŗ��Ă��܂����B
�@�����ŁA�t��������U�߂邱�Ƃɂ����B�����܂ŁA�����푈�ɂ���p�̐A���n������n�߂Ď����ǂ��悤�ɂ��ēǏ����Ă����B�ł́A�t�Ɍ��݂�����j��k��悤�ɂ��ēǏ����Ă������Ȃ�A�Ȃɂ������邾�낤���B
�@���ЂɊW���A��O�Ɛ����Ȃ��L�[�p�[�\���́A�ԈႢ�Ȃ��ݐM��B�������݂͌����A�V�Ԃł���A�e�ՂȂ��Ƃł͐K�����o���Ȃ��B�Ȃ�A���݂���݂ւƑk��`�œǏ�����A�Ȃɂ��������Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@�Ƃ����킯�œǂ̂�������グ��w���{�O��x���B
 �@�ǂ�ŁA�ŏ��́u���s�����v�Ǝv�����B�ݐM��������Ă���Ɠǂ̂����A���ۂɂ͖{���Ŏ��グ��u���{�O��v�Ƃ݂͊̌n���ł͂Ȃ��A���{�Ƃ̌n���������{���i���ׁE����A1894�`1946�j�A���{�W���Y�i���ׁE���낤�A1924�`1991�j�A���{�W�O�i���ׁE�����A1954�`2022�j�������̂ł���i�R�l�Ƃ��̐l�ł���̂ŁA�{�e�ł͌h�̗��Ƃ���j�B���A�ǂ�ŋ��������B�O�O�ɏ،����W�߂Ă������ƂŁA���{�W�O�Ƃ����l�̕����Ă��������ƂƂ��Ă̌��_�A���_��2017�N�̎��_�ł��ꂢ�ɂ�����o���Ă���̂ł���B
�@�ǂ�ŁA�ŏ��́u���s�����v�Ǝv�����B�ݐM��������Ă���Ɠǂ̂����A���ۂɂ͖{���Ŏ��グ��u���{�O��v�Ƃ݂͊̌n���ł͂Ȃ��A���{�Ƃ̌n���������{���i���ׁE����A1894�`1946�j�A���{�W���Y�i���ׁE���낤�A1924�`1991�j�A���{�W�O�i���ׁE�����A1954�`2022�j�������̂ł���i�R�l�Ƃ��̐l�ł���̂ŁA�{�e�ł͌h�̗��Ƃ���j�B���A�ǂ�ŋ��������B�O�O�ɏ،����W�߂Ă������ƂŁA���{�W�O�Ƃ����l�̕����Ă��������ƂƂ��Ă̌��_�A���_��2017�N�̎��_�ł��ꂢ�ɂ�����o���Ă���̂ł���B
�@�{���́A�܂��T�����wAERA�x2015�N�W������2016�N�T���ɂ����ĂX��f�ڂ���A���̓��e�ɑ啝�ɉ��M���Ċ��������B���҂͋����ʐM�Ζ����o�ēƗ������m���t�B�N�V�����E���C�^�[�B�����E�Љ��Ŏ��M�����𑱂��Ă���A�w���{�̌����x�@�x�i�u�k�Ќ���V���j�A�w���|�@���ƌ��́x�i�g�����X�r���[�j�A�w���{��c�̐��́x�i���}�АV���j�A�w���B�����Ɓx�i�͏o���Ɂj�Ȃǂ̒��������B
�@�{���́A���{�Ƃ���o���R�l�̐����Ƃ��A�u��ꕔ�F���v�A�u��F�W���Y�v�A�u��O���F�W�O�v�Ǝ����ǂ��Ĉ�l���L�q���Ă����B�L�q�ɂ������āA���҂͓O�ꂵ����ނ��s���Ă���B���{�Ƃ̒n���ł���R��������s���J���A����ÌS���u���i�ւ��ނ�j�ɒʂ��l�߁A����ɉ��ւ̊W�҂���ނ��A���E�W���Y�E�W�O�ځA�Ԑڂɒm��l�ɉ���Ęb���A�R�l�̐l�Ԑ��̉���܂ł��@��N�������Ƃ���B
�@��ނɉ������l�X�̑����͍���B���R�ł���B���������ŕa�������̂�1946�N�̂��Ƃ��B���ڒm��l�ƂȂ�ƁA���������ƂƂ��Ċ������Ă��������ɂ͎q�ǂ������҂̔N��ł������l�Ɍ�����B��ށE���M�̎����ł�����2010�N��O���́A���̂悤�ȍ�Ƃ��\�Ȃ��肬��̎����������Ƃ����邾�낤�B2023�N�̍��A�{���ɋM�d�ȏ،����₵�Ă��ꂽ���X�́A���̂قƂ�ǂ��S�Ђɓ���ꂽ�̂ł͂Ȃ��낤���B
�@�������Č@��N���������{���̏ё��́A�c�ɂ̗T���ȉƒ�ɐ��܂�������ɉ��x���ł��̂߂���A�Ȃ����N���オ���Ă����S�苭���ƁA�����ɂ���Ȃ�u�����v�Ƃ����`�e���悤�̂Ȃ��l�i�I�^���������ō\������Ă���B
�@���{���́A1894�N�i����27�N�j���u���̑�n��̉Ƃɐ��܂��B�������A���͐��܂�ĂP�N�����Ȃ������ɁA����R�̎��ɕa�C�ő������Ă��܂��A����Ɉ�Ă���B�c�������w�D�G�ŋ���̋�����l�����w�Z���o�ē����鍑��w�����w�Ȃɐi�w�B�����Ƃ��u�]�����͔̂��ꂪ���߂����炾�Ƃ����B������呲�ƌ�A�����Ŏ��]�Ԑ����Ƃ𗧂��グ��B�u�����ɂ̓J�l��������B�܂��J�l�����˂Ȃ�ʁv�ƍl�������炾�����B�₪�ėב��̖��Ƃ̖��E�Îq�ƌ������A��l���q�̐W���Y�����܂ꂽ�B
�@�������A1923�N�Ɋ֓���k�Ђ������B�����炭�͑����̔�Q�����̂��낤�B���͎��]�Ԑ����Ƃ����ŋA�����邱�Ƃ�]�V�Ȃ������B�������A�Îq�Ɨ����B���̗����͓��l���m���]���̂ł͂Ȃ��A��ɐÎq�̎��Ƃ̂Ȃ�炩�̎���ɂ����̂������炵���B���̌�A�����č����邱�Ƃ͂Ȃ������B
�@�A����A1928�N�i���a�R�N�j�̏O�c�@�I���ɗ���₵�������I�B�������������M���āA���͊w������ɜ늳���A��x�͗������Ă������j���������Ă��܂��B���̊����A���u�������������ɒS���o�����B�������u�����c��͓�Ɋ���čR�����J��Ԃ��Ă���A���̒���𖼉Əo�g�Ŋw���̂��銰�ɑ������̂ł���B���́u�a�g�ł��ǂ����v�Ɩ₤�āA�������ƃx�b�h����ɉ^�э���Ō��g�I�Ɏd�������A�����̐M���邱�ƂɂȂ����B
�@����̑I���n�Ղ����́A1935�N�i���a10�N�j�ɎR�����c��c���I���ɏo�n���A���I�B�����͑����Ƃ̌�����������Ă����̂ŁA���������c��c���ƂȂ����B������x���j���������Ƃ���A1937�N�i���a12�N�j�ɁA�ēx�O�c�@�c���I���ɑł��ďo�āA���x�͎R�����œ��I����B�I���ɂ������Ċ��́A���Ō����}�j�t�F�X�g�ɑ�������ӌ�����z�z�����B���̓��e�͓O�ꂵ�����핽�a��`�ƁA�n�x�i���̐����E���Ǝґ�ł������B���҂͂����Ɋ��́u�����̒Ⴓ�v�A�܂�푈�̂Ȃ����a�ȎЉ���������ď����Ƌ��ɕ��݁A���̐��������コ����Ƃ����ӎu�����Ă���B
�@����������͂ǂ����悤���Ȃ��A�푈�ւƗ���Ă����B�c���Ȃ肽�Ă̊��ɍ�����ł̉e���͂͂Ȃ��A����ǂ��납1940�N�i���a15�N�j�吭���^���������A���a��`���咣���邱�Ƃ������Ȃ��Ă����B
�@�ΕĊJ����1942�N�i���a17�N�j�S���̏O�c�@�c���I���́A���{�����E�����u���E���v����̂ƂȂ�A�u�吭���^�I���v�ƌĂ��B���̑I���ɁA���͎��̓����p�@�̓��t�ɐ^�������甽���A�E���Ƃ��ė���₵���B�E���ɂ͎����㐭�{�̌��F�̂��Ɨl�X�Ȍ����点��I���W�Q���s��ꂽ���A����ł����͓��I���ʂ����B����́A�ނ��ǂꂾ���n���ŕ���Ă������Ƃ������Ƃ��������̂��낤�B
�@���̎��A�ݐM��͓����p�@�Ɏ������āA���{���E���Ƃ��ėׂ̎R�����ɏ��o�n�B�g�b�v�œ��I���Ă���B�����p�@�ւ̐ڋ߂̂��߂ɖ��ɗ������̂��A���Љ��E������̒������z�̃J�l�ł������B
�@�s�킪�߂Â�1945�N�i���a20�N�j�t�A��̏ے��I�ȏo�������������B�ЂƂ͊��ƊݐM��̖ʉ�B���핽�a�����߂銰�ƁA�t�@�V�X�g�̊ݐM��͐����I����͂܂������قȂ������A�ׂ̑I����ŔE���Ȃ��瓖�I���A�߂��Ȃ��Ȃ������A�݂͕]�����Ă����悤�ł���B���̖ʉ��ɁA���q�̐W���Y�ƁA�݂̖��E�m�q�Ƃ̌����ɂȂ����Ă����B
�@�������A�C�R����q����ɓ������Ă������q�E�W���Y���ꎞ�A������B���U�����u�肵�����̂́u�̋��ɕʂ�������Ă����v�̋A���������B��ɐW���Y�͂��̎u����u��x���R�l�ɂȂ肽���Ǝv��Ȃ������B�w�ǂ������ʂȂ�X�����U�肽���x�Ƃ����C�������炾�����v�Ɖ�z���Ă���B�ǂ������ʂȂ焟���܂�u��͌`����ŁA�u�肵�Ȃ��Ƃ����I�����͂Ȃ������̂��B
�@���̑̒��͂܂��������Ă����B���̋A���ŕ��͑��q�Ɍ������Č�����B�u���̐푈�͕����邾�낤�B�����A�s���̓��{���S�z���B�Ⴂ�͂��ǂ����Ă��K�v�ɂȂ�B���ʂȎ��ɕ�������ȁv�B
�@�s���A���͐����������ĊJ���悤�Ƃ��邪�A�̒�������������Ȃ������B1946�N�i���a21�N�j�P�������B�����āA���������͑��q�̐W���Y�ւƈ����p����Ă����̂ł���B
�@��̎���ł�����{�W���Y�͏I���u�����͊ݐM��̖����ł͂Ȃ��A���{���̑��q���v�Ə̂��A�Ȃɂ��ƕ��E���̎v���o�b�������Ƃ����B���҂ɂ��n���ł��k���Ȏ�ނ��畂���яオ��̂́A���͕a�g�����Z�̐����ƂŁA���ꂪ�s�݂̉ƒ�ň�����ǓƁA�₵���ł���B
�@�����ǂ��Đ��їD�G�A�啿�ŃX�|�[�c���\�B�w�Z�ł͈�ڒu����鑶�݄����������S�̉���Ɏ₵�����B�����ނ́A���R�̋�����Z�����w�Z���瓌�����@�w���ɐi�w������A��Lj����ɔ����C�R�q����ɓ����B�����o�傷����X�𑗂�B�s���A���̎��ɔ�����p�Җ�肪�������邪�A����21�̔ނ͔�I��������Ȃ������B�Ȃ��Ƃ��ďO�c�@�c���ƂȂ����e�ʂ̈�t�E�ؑ��`�Y�́A�펞���ɑ吭���^��ƊW���Ă������߂Ɍ��E�Ǖ��ɂЂ��������Ď��E�B�����ė����������o�g�̎����p�Y�́A���̌㒆�����E�Œ����ɒn�����ł߂Ă������A���h���A���̎d�����p�����Ƃ����W���Y�ɂƂ��Ă͏�Q�ƂȂ��Ă����B
�@������呲�ƌ�A�����V���ɏA�E���Đ������L�҂ƂȂ�A1951�N�ɗm�q�ƌ����B�ݐM���联��ɘA�Ȃ����킯���B
�@1953�N�Ɍ��E�Ǖ����������݂����E�ɕ��A�������Ƃ���A�W���Y�̐l���������o���B1956�N�ɖ����V���������Ċ݂̔鏑���ƂȂ�A1958�N�Ɏ�����O�c�@�c���I���ɎR����悩��o�n�B�����������ł́A���łɎ����p�Y���n�Ղ��ł߂Ă����B���̖��͌��ǁA�݂̒�̍����h�삪������U�邢�A�R�����̎����}�c���̂ЂƂ�ɎQ�c�@�ɉ�邱�Ƃ����m�����ĉ��������B�������A�e���肾�����͂��̑I���n�Ղ́A10�N�ȏ�̋̌��ʁA�����̂��̂ƂȂ��Ă��܂��Ă����B�����Œn�Ղ�����Ă����˂Ȃ�Ȃ��B
�@���E���Ƌ`���݂͍̊l�������قȂ�B�������A���݂̊ɗ���˂Ύ����͓��I�ł��Ȃ������{�����猩���Ă���̂́A�W���Y���u�����Ɠ��ڂɂ��Ċ݂̈Ќ����o�b�N�ɂ����{���{���v�ƂƂ炦��Ǝ��������Ƃ������Ƃ��B���h���A���Ƃ͐����I����̈قȂ�ݐM����o�b�N�ɂ��Ȃ���Γ��I�͊o���Ȃ��Ƃ������ꂪ�A�W���Y���u����������Ă����������Ă�v�����^�����ƂւƓ����Ă����B
�@���ɋ����[���̂́A���ւ̍ݓ����N�l�Ƃ̊W�ł���B�R�����̑�s�s�ł��鉺�ւŁA�����W���Y�͒n���̖��ƁE�щƂ̎x�����Ă����B���������̗щƂ���A�ʎY�����o�g�̗ы`�Y���A�����ɑ����ďo�n���邱�ƂɂȂ�A�x�������Ȃ��Ȃ�B
�@�����Ŕނ��������̂��A���֍ݏZ�̍ݓ����N�l�̃R�~���j�e�B�������B���ւ͌Â����璩�N�����E�����嗤���ʂƂ̌�ʂ̗v���ł������B���������N��������s��܂ł́A���N�����͓��{�̐A���n�ł��������߁A���ւɂ͂��Ȃ�̋K�͂̒��N�l�R�~���j�e�B������̂��B�ނ玩�g�͓��{�̑I�����������Ȃ����A���ɂ̓r�W�l�X�Ő������ē��{�l�𑽐��ٗp���Ă���҂������B�g�D�[�Ƃ��ē����Ă����킯���B�����āA�ݓ����N�l�R�~���j�e�B�Ƃ��Ă��A�I�����������Ȃ����������̗��v���\���Ă���鐭���Ƃ��K�v�������B�����ĐW���Y�ɂ͒��N�l�ɑ��鍷�ʊ��o�͂Ȃ������B�����Z������ɁA���N�n�̐e�F������Ă�������ł���B
�@�����ł��ނ͑������闘�Q���A�������\���Ē�������Ƃ����ۑ�ɒ��ʂ��A�����^�����ƂƂ��Ă̋Z�ʂ�g�ɂ��Ă����B�������{���̋L�q���琄�@����ɁA�����̃v���Z�X�őo������\���Ɏ��������āA�����𗧂Ăđo���̖����̂��������Ă����Ƃ������ƂŁA�l�ԓI�ȉ�ʂƗ͗ʂ��グ�Ă��������Ƃ������Ă���B
�@���҂́A���̍��{�Ɂu�c�����̋����v�A�܂�ǓƂ�₵�����������̂ł͂Ȃ����Ɛ�������B���̐�����̌ǓƂ�m�邩�炱���A���҂̂炳��������邱�Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����A�ƁB
�@�{���͔M�S�Ɉ��{�W���Y�������������֍ݓ��ꐢ�̑啨�A�g�{�͎��̌��t���Љ�Ă���B
�u���̐l�i�W���Y�j�͐g��肪�Ȃ��B���e�����炸�A�Z������Ȃ��B���ꂪ�Ȃ��A��l�ł�����Ă����B����Ӗ��A�ݓ��Ǝ��Ă����B���ׂ͍����A�ڐ��͓����������v�@(�{��p.151)
�@���{�W���Y�͂��̌㏇���Ɏ����}���̒n�����ł߁A1986�N�ɂ͕��c���v���畟�c�h������Ĕh���̒��ƂȂ�B�u���͑�����b�v�Ƃ̕]���͍����������A1988�N�̃��N���[�g�����Ɉ���������ސT��]�V�Ȃ�����A�قǂȂ��K���������Ă��܂��B1991�N�T���ɁA�����̍��ɏA�����ƂȂ�67�Ŏ����B
�@�ŔӔN�A�ނ͕��Ɨ��������ꂪ�č����Ĉ�q�𐬂��Ă������Ƃ�m��B�ނ́u�����ɂ͒킪�����v�Ƒ傢�Ɋ�сA�����ʉ�Č�F�����B���ٕ̈���E�������Y�́A�W���Y�̍Ŋ����Ŏ�邱�ƂƂȂ����B
�@�W���Y�Ƃ��̎��ӂ́A�����ւ̎��O�́A���j�̐W�O�Ɉ����p����邱�ƂɂȂ�B
�@�Ƃ��낪�A�u��O���F�W�O�v�̋L�q�́A�����܂ł́u��ꕔ�F���v�A�u��F�W���Y�v�Ƃ͂܂��������͋C���ω�����B���҂��k���Ȏ�ނ��A�O�ꂵ�ĊW�҂ɉ���Đl�ԂƂ��Ă̗L��l���o���Ă����ԓx���ς��͂Ȃ��̂ɁA��C�ɓ��e��������ɂȂ�̂��B����͎�ޑΏۂƂȂ������{�W�O�Ƃ����l�̐l�Ԑ��̔����A���݂̂Ȃ��̌��ʂł���B
�@���{�����A���{�W���Y���A���ꂼ��̐l�ԂƂ��Ă̌��݂������Ă����B�����Ȃ鋫���ɐ��܂�A�����l���A�ǂ̂悤�ɂ��Č��f���A�����̐l���������Ő���Ƃ��������͂�����ƕ��������B
�@�������A���{�W�O�̎�ނ���́A���̂悤�Ȃ��̂���،����Ă��Ȃ��B�W�҂���̕������̌��ʌ����Ă���̂́A�b�܂ꂽ�����̒��A��̓I�ɉ�����I�ю�邱�ƂȂ��A���f���邱�Ƃ��Ȃ��A�ˋC���P�����邱�Ƃ��Ȃ��A�����Ȃ�ƂȂ��Ղ��ɗ��ꂽ���ʁA�����ƂɂȂ��Ă��܂����p�݂̂��B
�@�����炭�l�b�g�ɑ����M��Ȉ��{�x���҂́u����͒��҂��Ό��������Ă��邩�炾�v�Ǝ咣����Ƃ��낾�낤�B�Ƃ��낪�A�w������̗F�l��搶�A�T�����[�}������̏�i�A����ɂ͎��Z�̈��{���M���A���邢�͏��b�v�l�ɂ܂Ŏ�ނ����āA���̂��ׂĂ��s�C���Ȃ��炢�Ɉ�v���Ă���̂ł���B
�@�W�O�́A1954�N�i���a29�N�j�ɁA�W���Y�E�m�q�v�Ȃ̎��j�Ƃ��ē����Ő��܂��B���e�͎R���őI���n�Ղ��ł߂�̂ɖZ�����s�݂����B����ɂ��Ȃ��Ȃ���Ȃ�����M�������̂́A����̑c���E�ݐM������B���w�Z���琬���w���ɒʂ��A��؎��̍r�g�ɝ��܂�邱�ƂȂ�������w�@�w�������w�Ȃ𑲋ƁB���̂܂ܕč��ɗ��w�B���A���̕č��ł̊w������ɍ��̂ł��邱�Ƃ��\�I����ăX�L�����_���ɂȂ�B���̈�ۂ́u�����ƂɂȂ�܂ł̍��|���v�Ƃ��ē��Ђ����_�ː��|���ł��ς��Ȃ��B�u�v�̂͗ǂ����A��є����ėD�G�Ȃ킯�ł��A�S���_���Ȃ킯�ł��Ȃ��B�D�������e�͔����v�B�v����ɐM�O���Ȃ��B����W���Y�ɂ͂������A�l�Ƃ��Ĉ˂��ė����łȐc���Ȃ��B
�@���̈���ŁA�n���R���̎x���҂���A��w�ł̎w�������Ɏ���܂ł��A���t������b�ɂȂ��Ă���́A�W�O�̋��ʂƂ����ׂ������p����ᔻ����B�n���ł͌Ê��̎x���҂������āu��������W���Y����������ł͂Ȃ������v�ƒQ���B������w�Ŕނɍ��ې����w���������F�쐬���́A�W�O�̉����_���u�i�ނ́j���@���������������Ă��Ȃ��C�����܂��B����������ƌ��@��������ƕ����Ă��炢�����Ǝv���܂��v�Ƌ����ᔻ���A�ނ��i�߂����S�ۏ�@�����u���̍��ې����w�i�̎��Ɓj�������ƕ����Ă����̂��ȁA�Ǝv���܂��v�Ɣ����B���E�W���Y�̒�E�������Y�ł������A�W�O�̋��d�Ȑ����I�ԓx�ɋꌾ���悤�Ƃ��Ă������Ƃ����炩�ɂȂ�B
�@���̂��悻�A�D�ꂽ�����������Ȃ��O��ڂ́A�Q�x�ڂ̓��t������b�̐E�ɂ����ē��{���ǂ��ɓ����̂��A�Ƃ�����@���ŁA2017�N�o�ł̖{���͒��߂�������B
�@2022�N�V���W���A���{�W�O�͑I���V�����ɈÎE����A67�N�̐��U������B�����Ď���܂�B���j�I�l���Ƃ��Ă̈��{�W�O�̕]���͂��ꂩ�炪�܂��ɖ{�Ԃł����āA���ۂ��̂P�N�ŁA���O�ɂ͕�����Ȃ��������ƁA���邢�͖{���o�Ŏ���2017�N�ɂ͕\�ɏo�Ă��Ȃ��������Ƃ�����������B
�@���̒��ŁA�{���������Ă��Ȃ��d��Ȏ����������B�ЂƂ́A�����ꋳ��Ƃ̊W���B���̌��ɂ��Ă͖{���Ɏ����I�ȋL�q������B�ݐM��̑��߂Ƃ��ďO�c�@�c�����U�����߁A���̌�����{�W�O���x�������������c�Łi�ӂ����E������A1927�`2017�j�̏،����B����}��������2012�N�A��}�ɓ]�����������}�̑��ّI�������Ă����B���c�ƈ��{�͖ʒk���A���̐ȂŐl�����������c�́A���{�W�O�Ɂu�ēx�����}���ق�ڎw���v�Ɣ������B���͓}�������̂悤�ȏ�ł͂Ȃ��Əa����{�ɁA���c�͂����������B
�u���ˁA���̂܂܂��Ɓw�G�O���S�̑�����b���x�ƌ�������B���Ƀ}�X�R�~�͂��������Ƃ�B���{�ƂƂ��āA�ݐM��̌n�����p���҂Ƃ��āA�����͂Ȃ�Ƃ��Ă����_���Ȃ�����̂ł͂Ȃ����ˁv�@�i�{��p.279�j
�@���ʂƂ��āA�ނ͂��̔N�X���̎����}���ّI�ɏo�n���A�Δj��j���đ��قɕ��A�B���N12���̏O�c�@�I���Ŗ���}���S�s�������ƂŁA���t������b�ɕԂ�炢���B
�@���҂́u���c�̎��B�������W�O�̌��ӂ̗��R�������킯�ł͂Ȃ����낤�v�Ə����B�����Ɂu��������Ȃ��́i�c���E�ݐM��ւ̑z���j�͏��F�A���P������Ƃ̏���ȃv���C�h�Ǝ��I�ȓs���ɉ߂��Ȃ��v�ƁA�a���Ď̂Ă�B���̏�ŁA���҂̃C���^�r���[�ɉ����������Ƃ̌Éꐽ�i1940�`�j�̌��t�����p����̂��B�u�c��������ǂ��z�������Ƃ��A��������ǂ��z�������Ȃ�Ă����̂́A�{���̐����̎u�Ƃ͈Ⴄ�v�����B
�@�W�O����̕ŁA�����ꋳ��Ƃ̊W���A���̂Q�x�ڂ̎A�C�̂����肩�狭�܂������Ƃ��������Ă���B�c���ɋ����z��������ނ��A���c�Ȃǂ̐������@�ɁA�c���̈₵�������ꋳ��Ƃ̃R�l�N�V�������ő���Ɋ��p���A�c���̎v���c�����������@�������������悤�ƍl�����Ƃ����̂́A���蓾��悤�Ɏv����B
�@�u�v�̂͗ǂ����A��є����ėD�G�Ȃ킯�ł��A�S���_���Ȃ킯�ł��Ȃ��B�D�������e�͔����v�l�����A�̌����ɑς��邾���̎�����x����m�ł���c�����Ƃ��Ƃ���A�c�����ɓM�����Ă��ꂽ�c���̖ʉe�ɂ����邵���Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�@�����A����͒��҂��A�����ČÉꐽ���w�E����ʂ�A�܂������u�����̎u�v�ł͂Ȃ��B
�@�����ЂƂA�{���ŐG��Ă��Ȃ��͔̂ނ̌��N��肾�B�ނ��Ⴂ�������ᇐ��咰���i�N���[���a�j�Ƃ��������̓�a�������Ă������Ƃ͏O�m�̂��Ƃ��B�Q���ڂ̎��͕\�����Ắu�V�����������̂Łv�Ɛ������Ă������A�ނ��e�[�}�Ƃ����h�L�������^���[�f��w�d���̑��x�i���R�Y�l�ēA2023�N���J�j�ł́A��t�c���t���ēO�ꂵ�����N�Ǘ����s���Ďx���Ă������Ƃ��W�҂��،����Ă���B
�@�w�d���̑��x�ɂ͂����ЂƂC�ɂȂ�V�[��������B�C���^�r���[�����W�҂̂ЂƂ肪�u�ނ͒���1/3�Ȃ�����v�Ƃ����̂ł���B����͎��͊�Ȃ��Ƃń����Ƃ����̂̓N���[���a�̏ꍇ�A����1/3���؏�����Ƃ������Ƃ͂܂��Ȃ��̂��B��p�����x���J��Ԃ��Č��ʓI�ɒ���1/3�Ȃ��Ȃ�Ƃ������Ƃ͂��蓾�邪�A�ނ�����Ȃɉ��x�����؏��̎�p�����Ƃ����b�͕\�ɏo�Ă��Ȃ��B
�@�u����1/3�Ȃ��v�Ƃ����ƁA�l������̂́A�P�j��̏d�ŏo�������������N�����₷���������A�Q�j�q���V���X�v�����O�a�������炢�ł���B�P�j�͂��̂܂܂ł͎��S���Ă��܂��̂ŁA���₩�ɒ��̉������ʂ�؏�����K�v������B�Q�j�͐�V�I�ɒ��̈ꕔ�ɐ_�o���Ȃ��Ƃ����a�C���B��������_�o�̂Ȃ����ʂŏd�Ăȕ֔���N���������̊�@�ƂȂ�̂ŁA�_�o�̂Ȃ����ʂ�؏����ĂȂ����킹��K�v�������a�ł���B������ɂ���A�u�ނ͒���1/3�Ȃ�����v�Ƃ��������́A�ނ����ɓ�̕a�C���d�˂Ď����Ă����\������������B
�@�����Ē��ׂĂ݂�ƁA�ނ͎Q���ڂ�2013�N�T��19���ɁA��B��w�a�@���q���V���X�v�����O�a�̌��������@���邽�߂ɖK�₵�Ă���̂ł���B�܂�ނ́A�q���V���X�v�����O�a�ɓ��ʂ̋����������Ă����B
�@�ނ̎��a�ɂ��āA�x���҂����́u�a�C�ō��ʂ��ׂ��ł͂Ȃ��v�Ɨi�삵�Ă����B���A���͐��E�ɂ͈Öق̃��[�������݂���B
�@�u�a�C�̎҂͐ӔC����n�ʂɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�B
�@�a�C�Ő��������Ă͍����ɑ���`�����ʂ����Ȃ����A�a�C�̂��߂ɔ��f���݂�A���ꂱ�����̎������ɂȂ邩�炾�B
�@�ݐM��̃��C�o���ł��������X�R��1956�N12���A�ݐM���ނ��Ď����}���قƂȂ�A���t������b�ɏA�C�����B�������݂͕������ɉ�����B���A���N�P���A���͔]�[�ǂǂ���B�Ǐ�͌y�������ɉ�����̂Ǝv��ꂽ�B���ہA���̌����1973�N�܂Ő������̂ŁA���̂܂ܓ��t������b�߂��Ƃ��Ă����͋N���Ȃ������\�����傫���B���A���͐ӔC���ʂ����Ȃ��Ƃ��đ����ݔC65���Ŏ��E�B���̐Ȃ��݂ɏ������B
�@���t������b�̐Ӗ��͂��ꂮ�炢�ɏd���̂��B
�@���{�W�O���A���ɓ�̖�������Ȃ����������ڎw�����Ƃ�����A����͍����ւ̔w�M�ł���\�����l���˂Ȃ�Ȃ��B����ǂ��납�A���N�ł��邱�Ƃ���Ώ����̐����Ƃ��u�������Ƃ��̂��̂��ԈႢ�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�{���ŏ��b�v�l�́A�v�̂��Ƃ��u�f��ēɂȂ肽���l�������v�ƌ���Ă���B���邢�́A�����Ƃ̉Ƃɐ��܂�ĂȂ����f��̓��ɐi��ł����焟���t���I�ł͂��邪�A�ނ͐����ƂɕK�{�́u�����̉^���������Ő�v�̌������āA�����Ƃɑ�������������m���ł����̂�������Ȃ��B
�@������ɂ���A���j�I�l���Ƃ��Ă̈��{�W�O�̕]���͂܂��n�܂������肾�B�{���ɂ͂��̌����̈ꏕ�ƂȂ�A�M�d�ȏ،����l�܂��Ă���B
�y���Љ�����Ёz�@
���w���{�O��x
�� �� ���^�l�Z���^296�Ł^�i�ꒆ�^2017�N1�����^�����V���o�Ł^ISBN 9784023315433
https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=18758
���d�q���Ђ�����܂��B
����L�̒P�s�{�͔Ō��i�ꒆ�ŁA���ɔŁi���L�j������\�ł��B
�� �� ���^���ɔ��^328�Ł^�艿792�~�i�ō��j�^2019�N4�����^�����V���o�Ł^ISBN 9784022619617
https://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=20890
�u���Y�W��́g�Ǐ��m�[�g�h�v�@Copyright(c) ���Y�W��C2023
Shokabo-News No. 388�i2023-9�j�Ɍf���@
�y���Y�W���i�܂��炵���j����̃v���t�B�[���z�@
�m���t�B�N�V�����E���C�^�[�B1962�N�����s�o�g�B���݁A���o�r�W�l�X�I�����C���ɂāu�`�K�T�L���琢�Ԃ߂āv��A�ڂ̑��A�uModern Times�v�uViwes�v�u�e�N�m�g�����h�v�Ȃǂɕs����o�e���B�ߒ��Ɂw�ꂳ��A���߂�B�Q����50��Ɛg�j�̉�앱���L �O���[�v�z�[���ҁx�i���oBP�Ёj������B���̑��A�w���f���T���@�u�͂�Ԃ��Q�v�̒���x�w�͂�Ԃ��Q�̐^���x�w��ׁI�u�͂�Ԃ��v�x�w����̗L�l�F���D�x�w���� �X�y�[�X�V���g���̗����x�w����ׂ����H�x�w�̂���̐i���_�x�Ȃǒ��������B
Twitter�A�J�E���g�@https://twitter.com/ShinyaMatsuura
���u���Y�W��́g�Ǐ��m�[�g�h�v�́A�։ؖ[�̃��[���}�K�W���uShokabo-News�v�ɂĊu���ɘA�ڂ��Ă��܂��BWeb�T�C�g�ɂ̓��[���}�K�W���z�M��ɂȂ�ׂ����������Ɍf�ڂ���\��ł��B���[���}�K�W���ɂ��o�^���������B
�@�@�@�� Shokabo-News�̓o�^�E��~�E�A�h���X�ύX
| 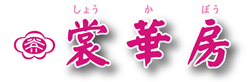 �@
�@ �y�։ؖ[�z ���[���}�K�W���uShokabo-News�v�A�ڃR�����@
�y�։ؖ[�z ���[���}�K�W���uShokabo-News�v�A�ڃR�����@