第68回 幽霊はここまで科学できる
『幽霊の脳科学』(古谷博和 著、ハヤカワ新書)
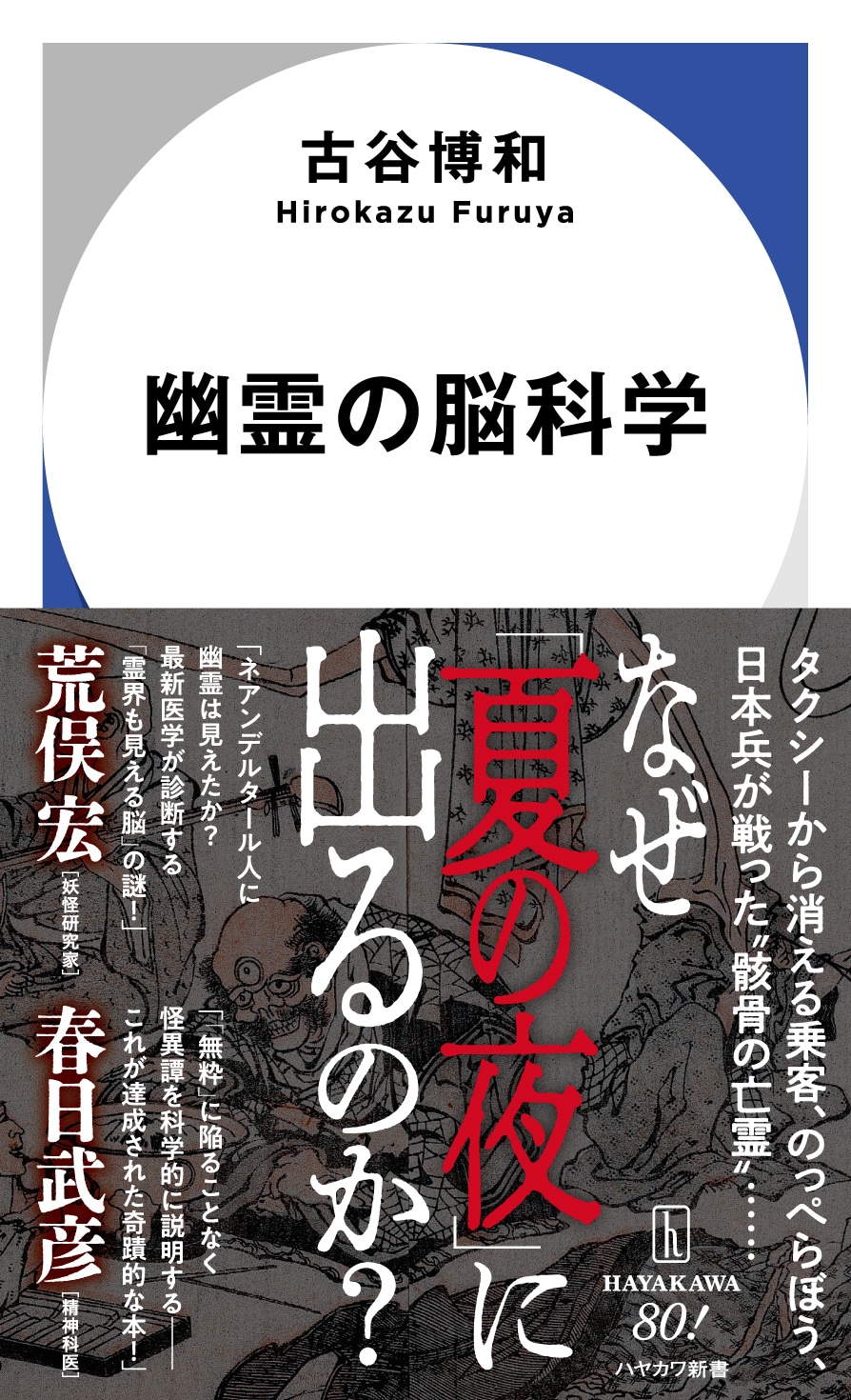 「幽霊の正体見たり枯れ尾花」という有名な川柳がある。が、この川柳は幽霊のなんたるかを全く説明していない。幽霊の実体は枯れ尾花であった、というのは説明になっていないのだ。
「幽霊の正体見たり枯れ尾花」という有名な川柳がある。が、この川柳は幽霊のなんたるかを全く説明していない。幽霊の実体は枯れ尾花であった、というのは説明になっていないのだ。
なぜ、枯れ尾花が幽霊に見えたのかを説明できて、初めて幽霊という現象を理解したことになる──こんな当たり前のことに、読後初めて気がついた。今回取り上げる『幽霊の脳科学』はそういう本だ。
著者は長らく高知大学医学部教授として、パーキンソン病や筋ジストロフィーなどの難治性神経疾患の研究をしてきた脳神経内科医。その傍ら、幽霊という現象に興味を持ち、脳科学の観点からの文献学的な研究も展開してきた。
本書を一言で要約すると「文献に記載された幽霊と言われる現象のうち、2/3は神経学や脳科学の観点から説明できる」というものだ。つまり人間の認知の仕組みの中に、「幽霊を見てしまう」機序が存在して、それが発動することで人は「幽霊を見た」という体験をするというのである。
近代的な物の見方からすれば、幽霊は実在するものではなく、人間存在の中に内在しているものが、何かの拍子に表に出てくるものだ。当たり前のことである。が、幽霊という現象がきちんと人間の認知の仕組みの側からひとつひとつ説明されるのは、ずいぶんと新鮮である。
近年の科学技術の進歩は、脳に針などを差し込むことなく、脳の内部でどのような活動が起きているかの観察を可能にした。fMRI(機能的磁気共鳴画像法)、NIRS(機能的近赤外分光法)、脳磁計(MEG:Magnetoencephalography)といった計測技術が実用化したことで、脳の部位別の機能や、各部位の役割や相互の影響は、かつてに比べれば遙かに精密に理解できるようになっている。
その知見を使って、過去の文献に記載された幽霊の目撃例を分析していくと、全体の2/3のケースにおいて、脳の機能と機序の側から説明が付くのだ。
本書は「幽霊の事例」とは書かずに「幽霊の症例」と書いている。そう、幽霊目撃の記録は著者にとって「症状の一例」なのである。
最初に分析の対象となるのは、ナルコレプシー(嗜眠症)という神経の病気の症状に類似した幽霊目撃の事例だ。ナルコレプシーは、日中に突然耐えがたい眠気に襲われて眠ってしまうという神経の病気だ。まだ、その原因は完全には解明されていないが、脳内における覚醒に関係する神経伝達物質のオレキシンの不足が発症に大きく関係していることが分かっている。
そこで、多くの幽霊目撃例を収集し、その中から、1)入眠時から覚醒時にかけて起きている、2)幻覚がある、3)幻聴がある、4)寝ているベッドが揺れるというような体感幻覚がある、5)意識は起きているが体が動かない金縛り現象がある──という特徴をもつケースをピックアップする。するとそのようなケースが多数存在することが分かる。上に上げた5つの条件は、ナルコレプシーの症状そのものだ。つまり、これらのケースに関してはナルコレプシーが原因と考えることが可能になる。
人間の睡眠は、夢を見るレム睡眠と夢を見ないノンレム睡眠とを繰り返す。レム睡眠時は、体の筋肉は弛緩していて動かない。ところがナルコレプシー患者の場合、レム睡眠とノンレム睡眠の交代パターンが崩れており、結果として夢の内容を現実に発生したこととして受け取ってしまうことが起きる。つまり、ナルコレプシーの症状と一致する幽霊目撃事例は、健康な人がなにかの拍子に、ナルコレプシーと同様の睡眠パターンの崩れた状態に入ってしまった結果ということになる。
では、どういう時に睡眠パターンが崩れるかというと、心身に過度のストレスがかかっている時だ。その観点で幽霊目撃事例を分析していくと、確かに先の5点を満たす幽霊目撃事例では、前後の状況から目撃者の心身に強いストレスがかかった状態だったと推察されるというのである。
この調子で、著者は幽霊目撃事例の中から類型的なパターンを見つけ出し、それに対応する神経学・脳科学的な機序を探し、うまく当てはまるものを見つけていく。例えば、夜間、タクシーなどに幽霊が乗ってきて消えてしまうというような事例には、ハイウェイ・ヒプノーシス(高速道路催眠現象)が原因ではないかとする。単調な道を走っていると眠気を催すという現象だ。この時、運転者に強いストレスがかかっているなどして眠りに入った直後にレム睡眠状態になると、ナルコレプシー同様に幻覚が発生するというわけである。
これだけなら、「単純に幽霊目撃事例の中から脳や神経の病気に当てはまりそうなものを選んだだけ」ということになりそうだが、今や前述したfMRIやNIRSなどの機器で、それぞれの状態のときに脳のどの部位がどのように活動しているかを調べられるようになっている。つまり幽霊目撃事例に対して「それは、脳のこの部位がこのような活動をして、それが脳の別の部位にこのように影響しているから」というような説明が付けられるようになっているのだ。
「幽霊は枯れ尾花だ」だけではなく、「なぜ枯れ尾花が幽霊に見えるのか」が、脳内で起きている物理的なプロセスとして説明可能なのである。
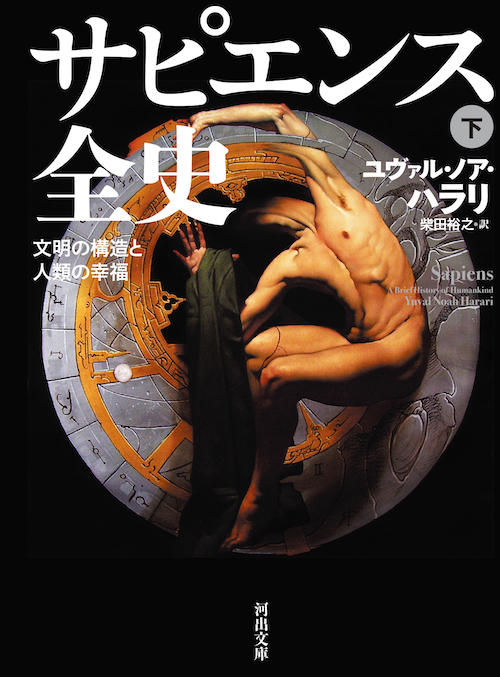
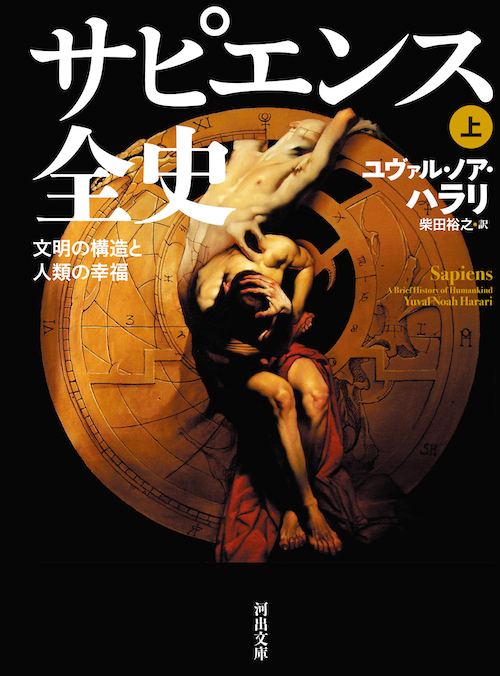 著者の分析は、幽霊目撃事例と脳の機能との対応というところに留まらない。そこからさらに、「なぜ人間は幽霊を見るようになったのか」という、ヒトという種の進化のあり方へと踏み込んでいく。そこで手がかりとなるのは、イス
ラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリの著した世界的ベストセラー『サピエンス全史』(2014年刊。邦訳は柴田裕之 訳、河出書房新社、2016年刊)だ。
著者の分析は、幽霊目撃事例と脳の機能との対応というところに留まらない。そこからさらに、「なぜ人間は幽霊を見るようになったのか」という、ヒトという種の進化のあり方へと踏み込んでいく。そこで手がかりとなるのは、イス
ラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリの著した世界的ベストセラー『サピエンス全史』(2014年刊。邦訳は柴田裕之 訳、河出書房新社、2016年刊)だ。
ハラリは『サピエンス全史』で、人類はまず約7万年前の“認知革命”で、大規模な集団をつくる能力を獲得したと主張する。ホモ・サピエンスは、約7万年前に、神や国家、貨幣など、現実の中に実体として存在するのではなく、想像の中に概念として存在するものを信じる能力を獲得した。だからこそ、大規模な集団をつくることができるようになり、ひいては文明を進歩させることができるようになったというのだ。
本書は、ハラリのこの主張を神経学・脳科学的に展開する。
「着衣失行」という高次脳機能障害の症状がある。高次脳機能障害とは、脳梗塞や事故による頭部への外傷、脳炎のような病気により脳の機能が阻害され、感情や行動のコントロールに問題が発生することだ。
着衣失行を発症した人は、衣服を着ることができなくなり、ただ衣服を体に巻くだけとなる。脳の損傷により、脳内で服の形状を思い描き、どこに首を通し、どこに腕を通すか判断することができなくなったのだ。
高次脳機能障害では、着衣失行に限らず、道具全般について観念失行という症状が発生する。患者は、その道具を手に取って使うことができる。しかし、目の前に道具がない状態では、その道具がどのようなものでどう使うかを説明できなくなってしまう。脳内にその道具のモデルを形成できないからだ。
一方で、チンパンジーのような類人猿は、着衣失行と同じく、服を与えても体に巻くことしかできないことが知られている。このことから著者は、現世人の我々ホモ・サピエンスと類人猿の違い、さらにはホモ・サピエンスと同時期に生存したがその後絶滅したネアンデルタール人やデニソワ人との違いは、脳裏に複雑な概念をモデル化し、しかもそのモデルを使って脳内で「どう動くか」「ここが変化することで、動作がどのように変化するか」といったことをシミュレートできるかどうかであろうと主張する。
ハラリの言う、神や国家、貨幣のような概念を信じる能力とは、これらの概念を脳内でモデル化し、しかもそのモデルを脳内で動かしてみて「ああなる、こうなる」とシミュレートできることではないか、というわけである。
別の言い方をすれば、類人猿やネアンデルタール人やデニソワ人は、観念失行の状態が自然で当たり前ということになる。
著者は、このヒトをヒトたらしめている、脳内での高次なモデル化とシミュレートの能力こそが、我々が幽霊を見るようになった理由ではなかろうかと推測する。強いストレスや睡眠不足、その結果発生するレム睡眠とノンレム睡眠の睡眠サイクルの乱れ、あるいは脳内での神経伝達物質の過剰や不足などから、脳内で必ずしも現実とは一致しない概念モデルが形成され、そのモデルを脳がシミュレートした結果、幽霊体験が生成するというわけである。
しかしながら、同時にこのような分析を行うことは「幽霊を科学的に解明して、駆逐することが目的ではない」とも書く。そして以下のような考え方を本書の最後で提示する。
「幽霊」あるいは「妖怪的なもの」というものは、決して「非科学的なもの」「無知な人間が信じる迷信」ではなくて、我々の脳の機能、人類の進化の過程でどのように認知機能が進化してきたを解明するための手掛かりを与えてくれるものと考えることができます。またその広がりは脳科学のみならず、生物学、社会学、宗教学、民俗学などを巻き込む広い裾野を持ったものです。そう考えると、「幽霊譚」に対して別の意味での興味が湧いてくるのではないでしょうか。
脳は人類の「最後のフロンティア」ともいえます。この「最後のフロンティア」にアプローチするには色々な道があるでしょうが、この本で述べてきたように「幽霊」もそのいくつもある道の一つかもしれません。
「幽霊」という主観がもたらす現象を、神経学・脳科学の最新の知見を使って、客観世界の現象と対応づけようとする大変面白い一冊である。
ところで──。
ハラリの『サピエンス全史』から、着衣失行の説明を経て、ヒトだけがもつ脳内における高次概念のモデル化とシミュレート能力に至り、そこから幽霊が生成するという著者の主張を読んでいて、私は思わず「あっ」と叫んでしまった。
 この連載のもう一方の執筆者で、2022年に亡くなられたサイエンス・ライターの鹿野司さんは、没後にまとめられた著書『サはサイエンスのサ[完全版]』(早川書房)で、何度も「人間が持つ認知の歪み」について言及していた。
この連載のもう一方の執筆者で、2022年に亡くなられたサイエンス・ライターの鹿野司さんは、没後にまとめられた著書『サはサイエンスのサ[完全版]』(早川書房)で、何度も「人間が持つ認知の歪み」について言及していた。
それはまさに『幽霊の脳科学』で著者が主張する脳内での高次概念のモデル化とシミュレートの能力のことではなかろうか。
そこから幽霊のようなものが発生してしまうことを、鹿野さんは「認知の歪み」と表現していたのではないか。
『サはサイエンスのサ[完全版]』を読み返してみると、鹿野さんはどうやら、心理学における「心の理論」という概念を手掛かりにして、「人間特有の認知の歪み」という考えに到達したようだ。「心の理論」とは、相手の考えていることを推し量る能力のことである。それは相手のモデルを脳内に生成して「あの人なら、ああ考える、こう考える」とシミュレートすることで達成される。
加えて鹿野さんは、チンパンジーなどの類人猿の研究をかなり深く調べた上で、「類人猿はありのままの自然を受け止め、認知しているが、人間は認知に歪みがあって、ありのままを受け止めることができない。しかし、その認知の歪みこそが人間を人間たらしめている」という認識に行き着いた。
「類人猿はありのままの自然を受け止める」は、『幽霊の脳科学』の「類人猿では、観念失行の状態が自然だ」という記述を別の言い回しで表現したものだろう。「認知の歪みこそが人間を人間たらしめている」という考えは、ハラリ著『サピエンス全史』における「認知革命」に、さらには『幽霊の脳科学』における脳内での高次概念のモデル化とシミュレートの能力にそれぞれ対応する。
つまり、鹿野さんが行き着いた人間の認知の歪みという考えは、『幽霊の脳科学』が描き出す脳内の高次概念のモデル化とそのシミュレートということを、別の方向から掘っていって別の言葉で表現したものではなかろうか。
この連載の『サはサイエンスのサ[完全版]』を取り上げた回(※)で、私は
20代から「ログイン」誌で長期連載した「オールザットウルトラ科学」がホップ、「サはサイエンスのサ」がステップなら、この次にはジャンプがあったのではなかろうか。もし鹿野さんが“ジャンプ”を書くことができたならば、それが南方熊楠が目指しつつも果たせなかった、主観と客観を統合した総合的な世界の見取り図の提示に至っていたのではないだろうか
と書いた。
※松浦晋也の“読書ノート” 第65回「鹿野さん、ごくろうさまっ」
https://www.shokabo.co.jp/column/matsu-65.html
どうも、本当に鹿野さんは、主観と客観を統合した総合的な世界の見取り図に向けた、ひとつのとっかかりを掴んでいたようである。あらためて、鹿野さんの早世が惜しまれる。
【今回ご紹介した書籍】
●『幽霊の脳科学』
古谷博和 著 /新書判/216頁/定価1254円(税込み)/2025年8月発行/
早川書房(ハヤカワ新書)/ISBN 978-4-15-340046-7 C0240
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000240046/
※電子書籍もあります。
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000614851/
●『サピエンス全史 上 −文明の構造と人類の幸福−』
ユヴァル・ノア・ハラリ 著、柴田裕之 訳/文庫判/360頁/定価1089円(税込み)/
2023年11月発行/河出書房新社(河出文庫)/ISBN 978-4-309-46788-7 C0122
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309467887/
●『サピエンス全史 下 −文明の構造と人類の幸福−』
ユヴァル・ノア・ハラリ 著、柴田裕之 訳/文庫判/400頁/定価1089円(税込み)/
2023年11月発行/河出書房新社(河出文庫)/ISBN 978-4-309-46789-4 C0122
https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309467894/
※上記2点の書誌データは2023年に刊行された文庫版のものです。
※電子書籍もあります。
●『サはサイエンスのサ[完全版]』
鹿野 司 著/A5判/648頁/定価4840円(税込み)/2024年9月25日発行/
早川書房/ISBN 978-4-15-210360-4 C0040
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0005210360/
※電子書籍もあります。
https://www.hayakawa-online.co.jp/shop/g/g0000614650/
「松浦晋也の“読書ノート”」 Copyright(c) 松浦晋也,2025
Shokabo-News No. 405(2025-8)に掲載
【松浦晋也(まつうらしんや)さんのプロフィール】
ノンフィクション・ライター。1962年東京都出身。現在、日経ビジネスオンラインにて「「チガサキから世間を眺めて」を連載中。近著に『ロケットサバイバル2030』(日経BP社)がある。その他、『母さん、ごめん。2』『日本の宇宙開発最前線』『小惑星探査機「はやぶさ2」の挑戦』『はやぶさ2の真実』『飛べ!「はやぶさ」』『われらの有人宇宙船』『増補 スペースシャトルの落日』『恐るべき旅路』『のりもの進化論』など著書多数。
Twitterアカウント https://x.com/ShinyaMatsuura
※「松浦晋也の“読書ノート”」は、裳華房のメールマガジン「Shokabo-News」にて隔月に連載しています。Webサイトにはメールマガジン配信後になるべく早い時期に掲載する予定です。是非メールマガジンにご登録ください。
→ Shokabo-Newsの登録・停止・アドレス変更
| 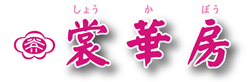
 【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム
【裳華房】 メールマガジン「Shokabo-News」連載コラム