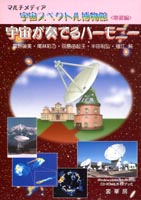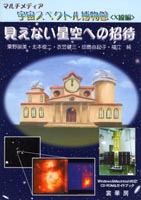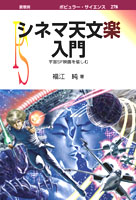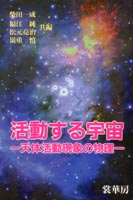|
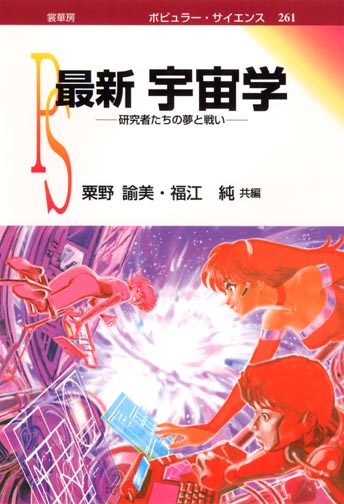
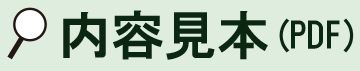
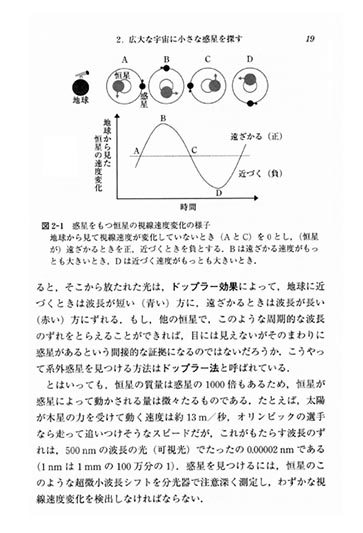


Amazon
楽天ブックス
セブンネットショッピング
Knowledge Worker
紀伊國屋書店
ヨドバシ・ドット・コム
ローチケHMV
e-hon
Honya Club
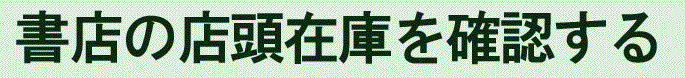
丸善,ジュンク堂書店,文教堂
紀伊國屋書店(新宿本店)
三省堂書店
有隣堂
くまざわ書店
コーチャンフォー
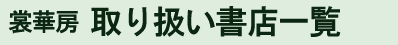

|
|

岡山天文博物館館長 粟野諭美・
大阪教育大学名誉教授 理博 福江 純 共編
四六判/244頁/定価2200円(本体2000円+税10%)/2004年5月発行
ISBN 978-4-7853-8761-7(旧ISBN 4-7853-8761-0)
C0044
激しく噴き出す太陽フレア、太陽系外惑星の探索、地球外文明(ET)探し、超巨大ブラックホールの存在と成因、震動する恒星、惑星系の誕生、変動する星の光、銀河の一生、重力レンズ現象とマッチョ、X線で輝く天体、銀河形成のシミュレーション、宇宙誕生直後の様子…。
地上の大型望遠鏡群や宇宙に浮かぶ探査機・天文衛星、可視光以外の光をとらえる観測技術、そしてコンピュータとシミュレーション技術などの進歩・発達によって、今まで想像もつかなかった宇宙の姿が明らかになってきました。
本書は、最新の宇宙像とその奥に潜む宇宙の“神秘”を、第一線で活躍する若手・中堅の研究者がわかりやすく紹介します。
世界天文年2009日本委員会公認書籍
(本文図版・イラスト/田巻久雄)
サポート情報
◎ まえがき
◎
編者インタビュー(アニマ・ソラリスのWebサイト)
◎ 正誤表
I 太陽系と宇宙人
1.フレアの統一モデル −太陽フレア,恒星フレア,原始星フレア−[柴田一成]
2.広大な宇宙に小さな惑星を探す −太陽系外惑星探し−[佐藤文衛]
3.これからのET探し [仲野 誠]
II 星とブラックホール
4.ブラックホールのミッシングリンク [福江 純]
5.星の調べを聴く [神戸栄治]
6.惑星系形成の始まり −オリオン・プロプリッド−[山下卓也]
7.できたての星の光の秘密 −偏光・測光観測からの情報−[松村雅文]
III 宇宙と銀河
8.銀河の一生 [富田晃彦]
9.宇宙に漂う望遠鏡 −もう一つのレンズと宇宙の蜃気楼−[米原厚憲]
10.まだまだあったX線天体 [北本俊二]
11.宇宙のリサイクルと銀河進化 [森 正夫]
12.宇宙の夜明け −宇宙暗黒時代と銀河宇宙の誕生−[梅村雅之]
まえがき
I 太陽系と宇宙人
1.フレアの統一モデル −太陽フレア,恒星フレア,原始星フレア−[柴田一成]
1.1 はじめに
1.2 太陽フレア
(1)「ようこう」ムービーからの新発見
(2)フレアの発生メカニズム
(3)リコネクション
(4)フレアの統一モデル
1.3 恒星フレアと原始星フレア
2.広大な宇宙に小さな惑星を探す −太陽系外惑星探し−[佐藤文衛]
2.1 はじめに
2.2 系外惑星の発見
2.3 視線速度精密測定
2.4 多様な系外惑星
(1)灼熱巨大惑星 −ホット・ジュピター−
(2)楕円軌道惑星 −エキセントリック・プラネット−
(3)太陽系に似た惑星系
2.5 惑星をもつ恒星の特徴
2.6 日本初の系外惑星発見
2.7 おわりに
3.これからのET探し [仲野 誠]
3.1 はじめに
3.2 SETIのアプローチ
3.3 電波によるSETI
(1)目標探査方式
(2)全方向探査システム
(3)おんぶ型SETI
3.4 光SETI(OSETI)
(1)光で通信する
(2)ペタワットレーザー
(3)始まったOSETI
3.5 SETIの未来は明るいか?
(1)SETIの通知表
(2)宇宙空間へ
(3)SETIは成功するか?
II 星とブラックホール
4.ブラックホールのミッシングリンク [福江 純]
4.1 わかっていたこと
(1)ブラックホールの実在
(2)ブラックホールの種類/超巨大ブラックホールの存在
(3)恒星ブラックホールの成因
4.2 わからなかったこと
(1)最初から
(2)星の潮汐破壊
(3)星の衝突破壊
(4)星間ガスの雨が降る
(5)巨大分子雲が突っ込む
(6)銀河相互作用
4.3 わかったこと −失われた環−
(1)中間質量ブラックホール
(2)その他の興味深い報告
4.4 わからなくなったこと −連続か断続か−
5.星の調べを聴く [神戸栄治]
5.1 はじめに
5.2 星の非動径振動とは
5.3 太陽の5分振動
5.4 日震学とその成果
5.5 星震学は夜明け間近
5.6 太陽型星の星震学
5.7 その他の星での星震学
6.惑星系形成の始まり −オリオン・プロプリッド−[山下卓也]
6.1 はじめに
6.2 プロプリッドと惑星系形成
6.3 プロプリッドの原始惑星系円盤
6.4 すばる望遠鏡による水素分子輝線の観測
(1)励起温度
(2)ダストの沈澱と成長
6.5 すばる望遠鏡による中間赤外線放射の観測
6.6 プロプリッドの惑星系形成の進化段階
6.7 おわりに
7.できたての星の光の秘密 −偏光・測光観測からの情報−[松村雅文]
7.1 はじめに
7.2 偏光とは
7.3 2グループあれば3グループある?
(1)堂平観測所での観測
(2)グリニンらのモデル
7.4 星でも眺めるか
7.5 おわりに −まだまだ秘密が?−
III 宇宙と銀河
8.銀河の一生 [富田晃彦]
8.1 星の一生,銀河の一生
8.2 銀河の一生の調べ方
8.3 銀河の“世論調査”
(1)宇宙論的星形成史
(2)ナンバー・カウントの解析
(3)ASTRO-FとALMA
8.4 銀河の“戸別訪問”
8.5 すばる望遠鏡の活躍
8.6 巨大なパズル再現の作業
9.宇宙に漂う望遠鏡 −もう一つのレンズと宇宙の蜃気楼−[米原厚憲]
9.1 新しい望遠鏡
(1)さまざまな望遠鏡
(2)重力レンズ現象とは?
(3)重力レンズの特性
(4)重力レンズ現象の利用法
9.2 マッチョ(MACHO)
(1)マッチョって何?
(2)マッチョを診る
9.3 双子のクェーサーと宇宙の大きさ
(1)宇宙の大きさを測る
(2)双子が教える宇宙の大きさ
9.4 クェーサーの心臓部を拡大する
9.5 宇宙最大級のレンズ
(1)銀河の塊でできたレンズ
(2)望遠鏡と呼ぶからには当然のこと
(3)銀河団は軽い? 重い?
9.6 おわりに
10.まだまだあったX線天体 [北本俊二]
10.1 はじめに
(1)X線とX線天文学
(2)X線天文衛星の活躍
10.2 星形成領域からのX線
(1)星形成領域
(2)クラス3やクラス2の天体からのX線
(3)クラス1とクラス0の天体からのX線
(4)褐色矮星からのX線
10.3 星からのX線
(1)太陽および晩期型星からのX線
(2)早期型星からのX線
(3)星風衝撃波モデル
(4)早期型星での高温成分の発見
10.4 銀河団の複雑な振る舞い
(1)高温プラズマとダークマター
(2)クーリングフロー・モデル
(3)「あすか」と「ニュートン」による観測
(4)「チャンドラ」による観測
10.5 活動銀河核からの鉄輝線
(1)ブラックホールの存在の証拠
(2)鉄輝線の強度と構造
10・6 おわりに
11.宇宙のリサイクルと銀河進化 [森 正夫]
11.1 宇宙の錬金術
(1)ビッグバンと元素の生成
(2)重元素の生成と宇宙のリサイクル
11.2 リチャードソンの夢
11.3 物質の循環と銀河進化論
11.4 銀河の化学力学進化シミュレーション
(1)矮小銀河のシミュレーション
(2)大質量原始銀河のシミュレーション
(3)宇宙論的シミュレーション
11.5 おわりに
12.宇宙の夜明け −宇宙暗黒時代と銀河宇宙の誕生−[梅村雅之]
12.1 ビッグバン宇宙
12.2 宇宙再電離
12.3 “化石の星”発見
(1)星形成のしくみ
(2)“最初”の星の誕生
12.4 宇宙の夜明け(宇宙再電離)
(1)大質量星かブラックホールか
(2)輻射輸送の計算と観測
12.5 銀河宇宙の誕生
あとがき
宇宙を知るための参考書
最新の宇宙を知るWWWサイト
天体名索引
事項索引
| 第1章 | 柴田一成 | (京都大学名誉教授) |
| 第2章 | 佐藤文衛 | (東京工業大学 理学院教授)
| | 第3章 | 仲野 誠 | (元 大分大学教授)
| | 第4章 | 福江 純 | (大阪教育大学名誉教授)
| | 第5章 | 神戸栄治 | (自然科学研究機構 国立天文台 岡山天体物理観測所特任准教授)
| | 第6章 | 山下卓也 | (自然科学研究機構 国立天文台 TMTプロジェクト教授)
| | 第7章 | 松村雅文 | (香川大学 教育学部教授)
| | 第8章 | 富田晃彦 | (和歌山大学 教育学部教授)
| | 第9章 | 米原厚憲 | (京都産業大学 理学部教授)
| | 第10章 | 北本俊二 | (立教大学 理学部教授)
| | 第11章 | 森 正夫 | (筑波大学 計算科学研究センター准教授)
| | 第12章 | 梅村雅之 | (筑波大学 計算科学研究センター教授)
| | (2021年7月15日現在) |
|
|
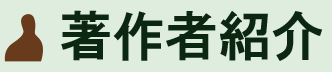
粟野 諭美
あわの ゆみ
東京都に生まれる。大阪教育大学教育学部卒業、大阪教育大学大学院修士課程修了。主な著書に『星空の遊び方』(共著、東京書籍)、『宇宙はどこまで明らかになったのか』『カラー図解でわかる光と色のしくみ』(以上 共著、SBクリエイティブ)などがある。
福江 純
ふくえ じゅん
1956年 山口県に生まれる。京都大学理学部卒業、京都大学大学院理学研究科博士課程修了。大阪教育大学助手・助教授・教授などを歴任。専門は降着円盤や宇宙ジェットに関する理論的研究。主な著書に『文系編集者がわかるまで書き直した世界一有名な数式「E=mc2」を証明する』(日本能率協会マネジメントセンター)、『90分でブラックホールがわかる本』(大和書房)、『極・宇宙を解く』(共編、恒星社厚生閣)、『「超」入門 相対性理論』(講談社)、『14歳からの天文学』(日本評論社)、『完全独習現代の宇宙物理学』(講談社)、『宇宙流体力学の基礎』(共著、日本評論社)などがある。
執筆者一覧
(情報は初版刊行時のものから一部修正しております)


天空からの虹色の便り
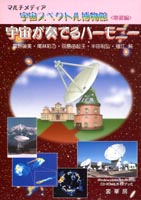
宇宙が奏でるハーモニー
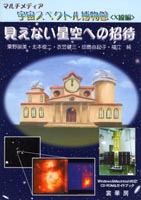
見えない星空への招待

SF天文学入門(上)

SF天文学入門(下)
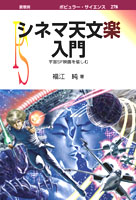
シネマ天文楽入門
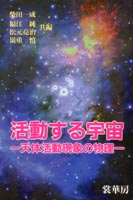
活動する宇宙


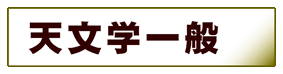



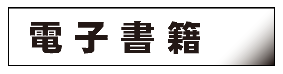

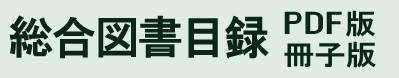


|
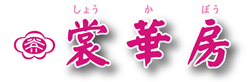
![]()
![]()